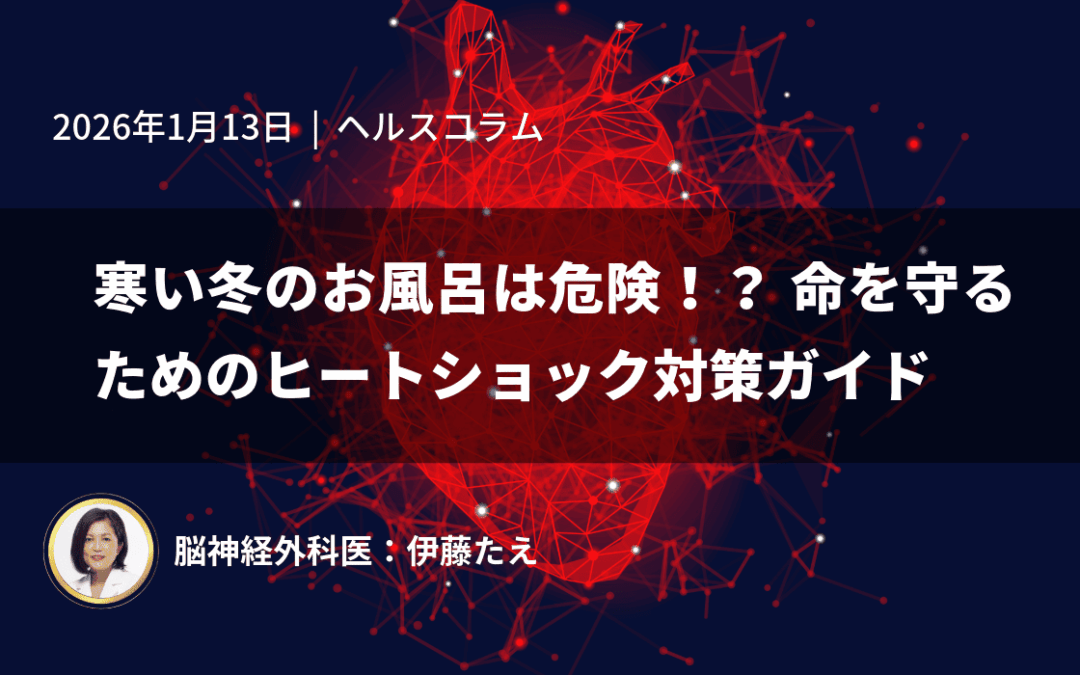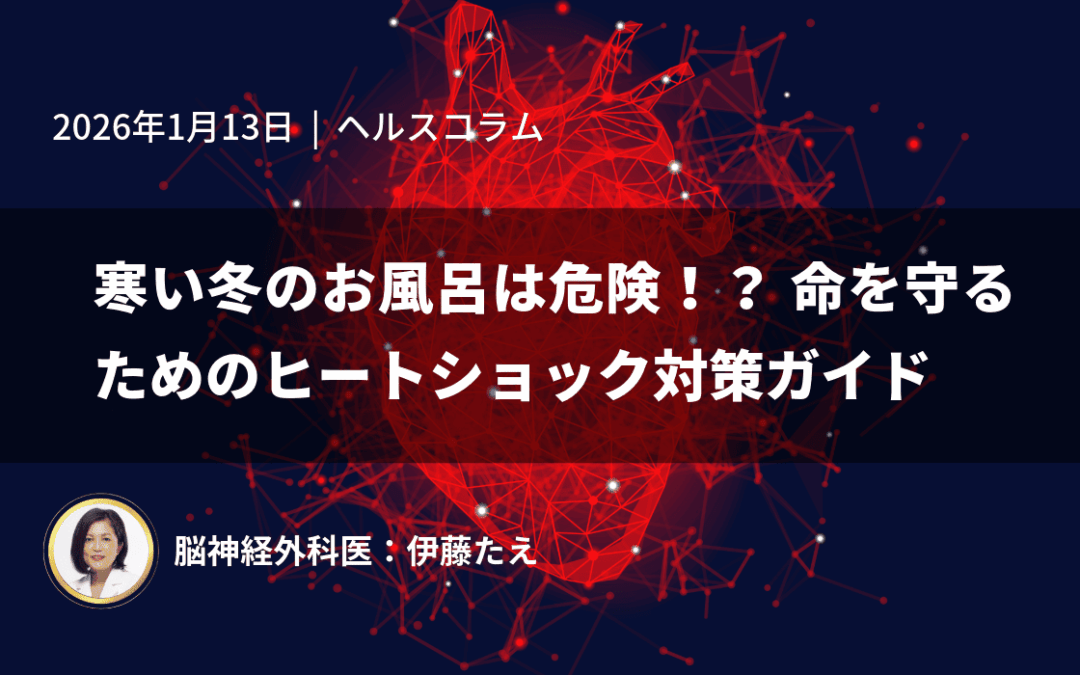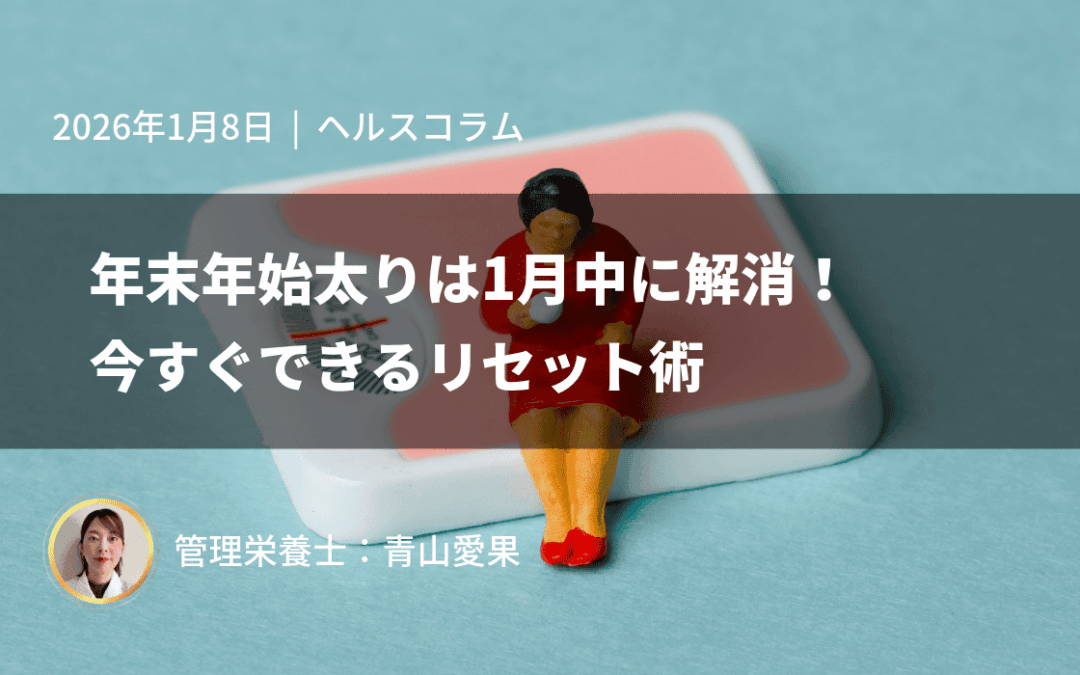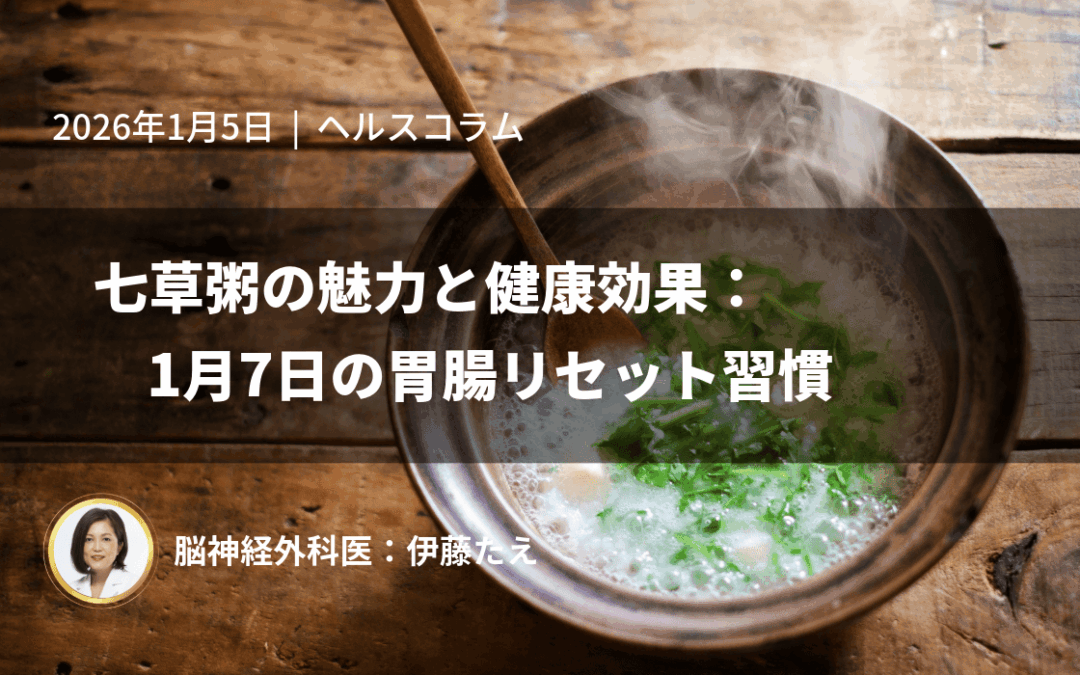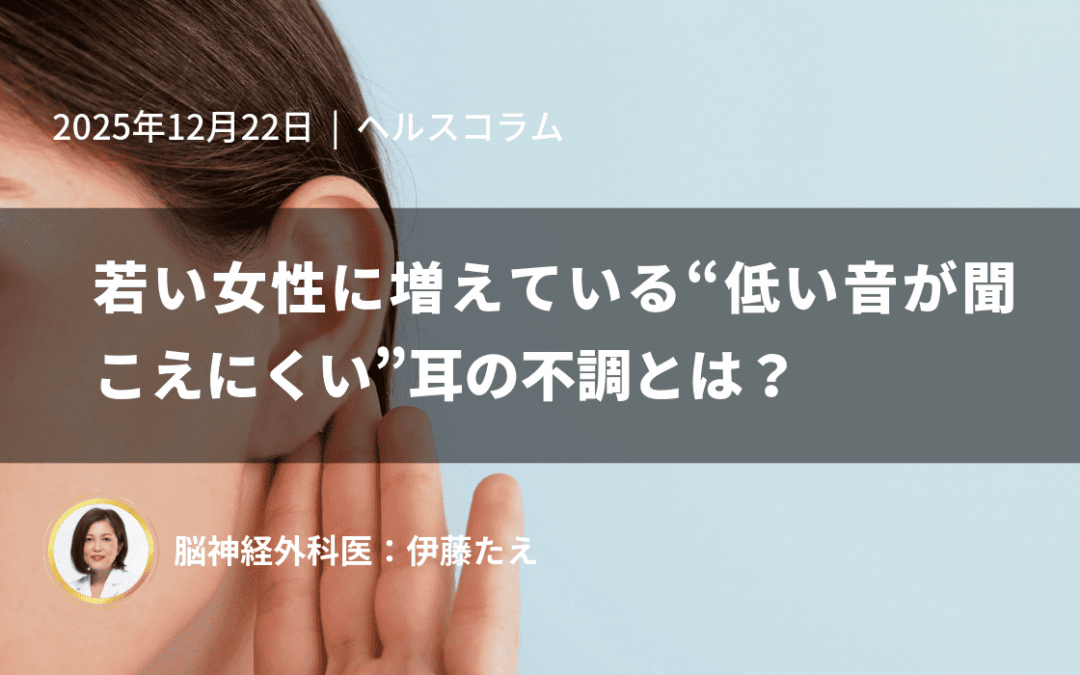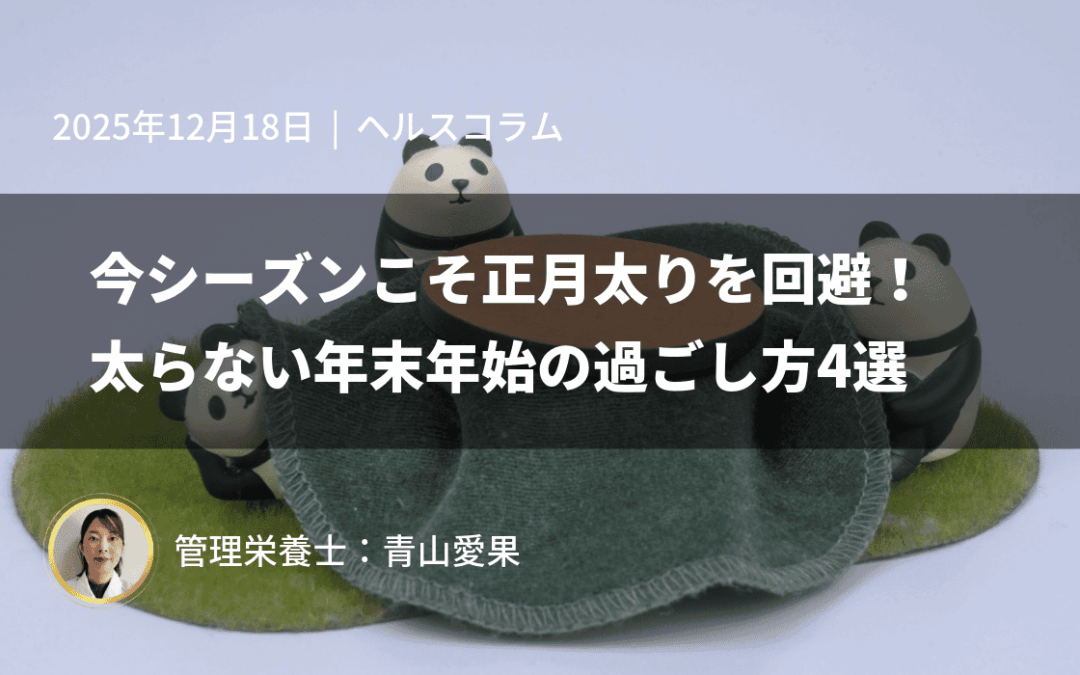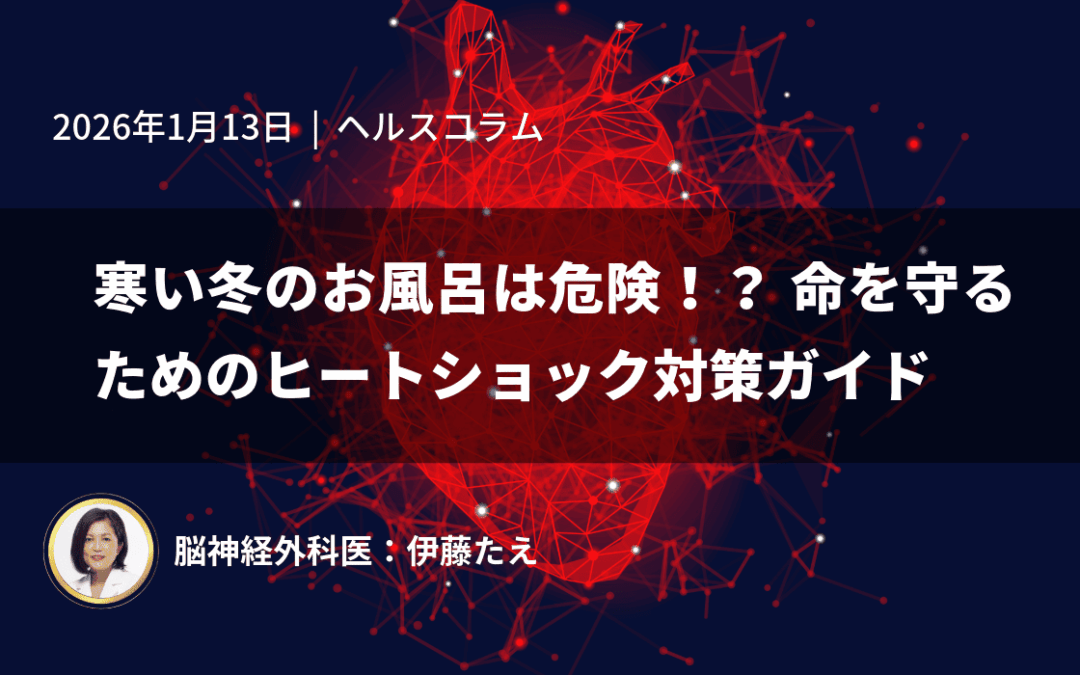
2026年1月13日 | ヘルスコラム
この記事の著者 とても寒い日が続きますが、元気にお過ごしでしょうか? このアプリを使っている皆さんは、日々の運動量や食事、睡眠の管理など、健康意識が高いと思われます。 しかし、冬に潜む、データにはなかなか現れにくい危険な現象があります。 それは、年間約1万9000人もの死者が出ているとも言われる「ヒートショック」です。 特に入浴中の事故は年間を通じて最も多く、冬場はそのリスクが一気に上昇します。 ご自身の健康はもちろん、ご両親の健康を気遣う方も多いと思われます。...
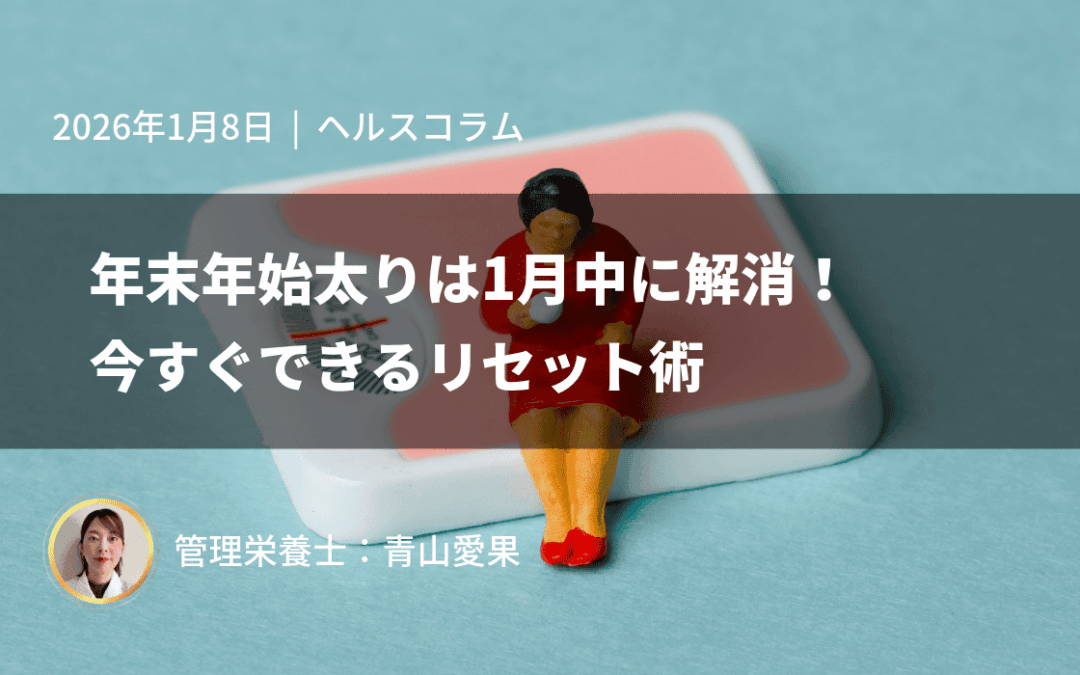
2026年1月8日 | ヘルスコラム
この記事の著者 楽しいイベントが盛りだくさんの年末年始。クリスマスパーティー、お正月の集まり、飲み会などで食べ過ぎていませんか? 「ちょっと太ったかも?」という方は、今が体重を戻すチャンスです。 増えてしまった体重を放置すると、体重がさらに右肩上がりになってしまい、元に戻すまで時間がかかってしまいます。 今回は、年末年始に増えた体重を1月中に戻すための方法をお伝えします。 年末年始太りを1月中に解消する3つのポイント 1年の頑張りをねぎらう年末やおめでたいお正月は、今まで我慢していた好物やお酒を解禁した方もいらっしゃるでしょう。...
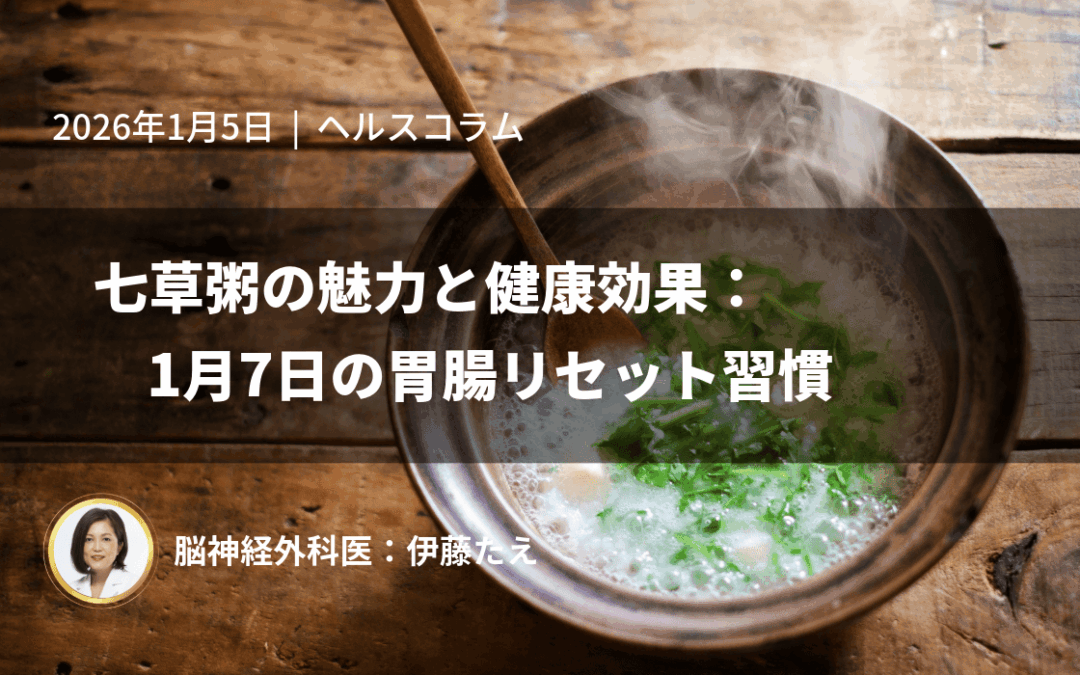
2026年1月5日 | ヘルスコラム
この記事の著者 お正月が終わるころ、なんとなく胃が重い、身体がむくむ、疲れが取れないなど、様々な不調を感じることがありませんか? そのタイミングで訪れるのが「七草粥(ななくさがゆ)」の日。 1月7日の朝に春の七草を加えたお粥をいただく、古くからの日本の習慣です。 「伝統行事のひとつ」と思われがちですが、医師の目線で見ても七草粥は健康的メリットが非常に多いです。 ただの風習以上に意味を持ち、身体と心の健康をサポートする素晴らしい知恵が詰まっています。 今回は、その七草粥について医学的な視点も交えて、お話させていただきます。...

2025年12月25日 | ヘルスコラム
この記事の著者 寒さの厳しい季節になり、手足の冷えに困っていませんか? 寒さ対策としてはもちろん、風邪予防としても体を温めたいところです。 今回は、冷え対策のために取り入れたい食材と、おすすめのレシピを紹介します。 辛味が苦手でもOK!体を温める温活食材 体の冷え対策は、腹巻や手袋などで防寒する方法や、入浴で体を温める方法があります。 それに加えて、温活食材を取り入れて体の内側から温めることがおすすめです。 体を温める食材として、しょうが、とうがらしが知られていますが、辛味が苦手な方もいらっしゃるでしょう。...
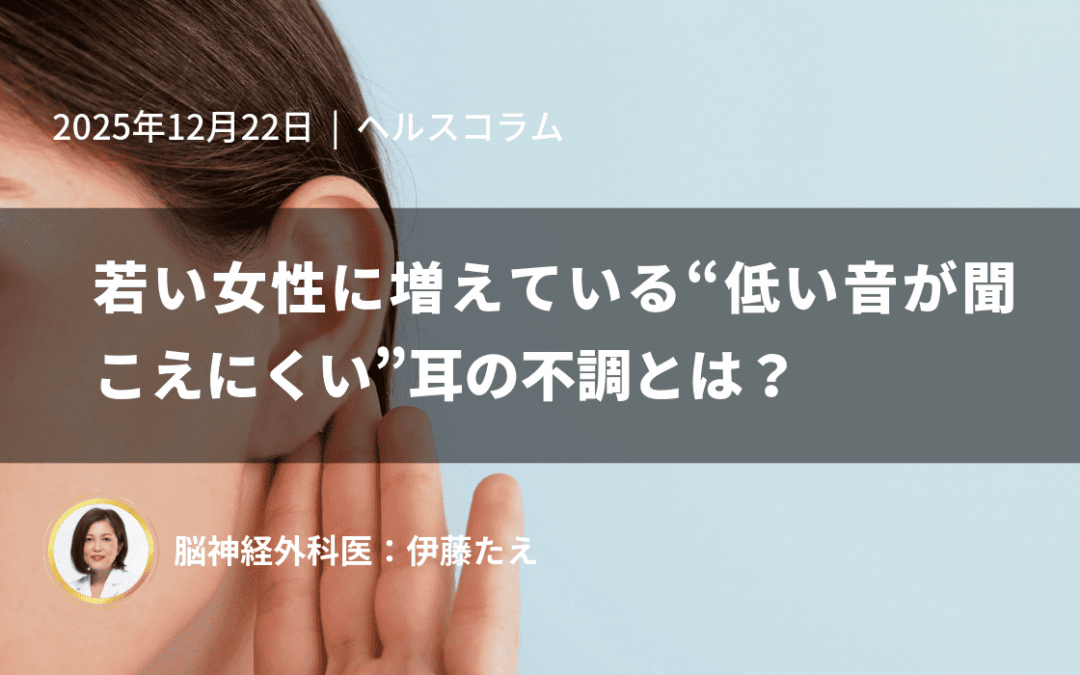
2025年12月22日 | ヘルスコラム
この記事の著者 最近、若い世代の女性で「耳の不調」を訴える方が増えています。 「耳が詰まった感じが取れない」「自分の声がこもる」「低い音が聞こえにくい」 そんな症状が続くことはありませんか? こうした症状の背景には、「低音障害型感音難聴」という病気が隠れている場合があります。 「難聴」というと高齢の方の病気という印象を持たれがちですが、この病気は働き盛りの20〜40代、特に頑張り屋の女性に多く見られます。...
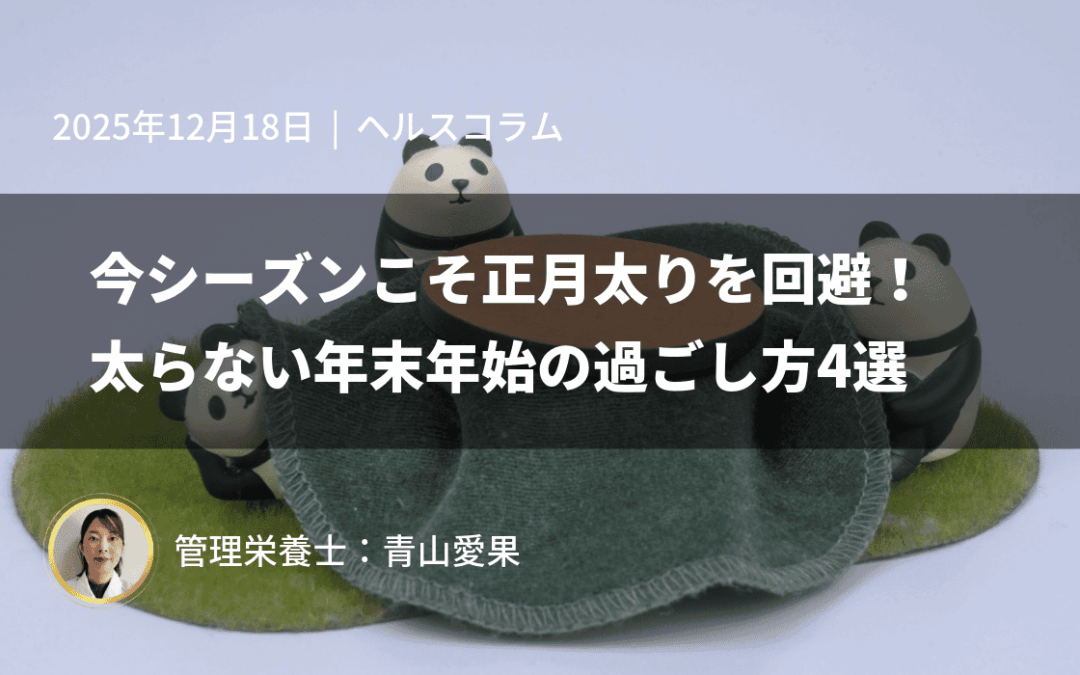
2025年12月18日 | ヘルスコラム
この記事の著者 年末年始に体重が増えてしまった経験はありませんか? クリスマス、お正月、飲み会などのイベントシーズンである年末年始は、つい食べ過ぎてしまいがち。 1度増えた体重を戻すのはとても大変であるため、今シーズンは体重をキープしたまま乗り越えたいものですよね。 今回は、年末年始に太らない過ごし方について紹介します。 年末年始に太るのはなぜ? クリスマスに始まり、お正月まで続く年末年始は、「せっかくだから食べちゃおう!」という気持ちで高カロリーメニューにも手が伸びやすくなります。...