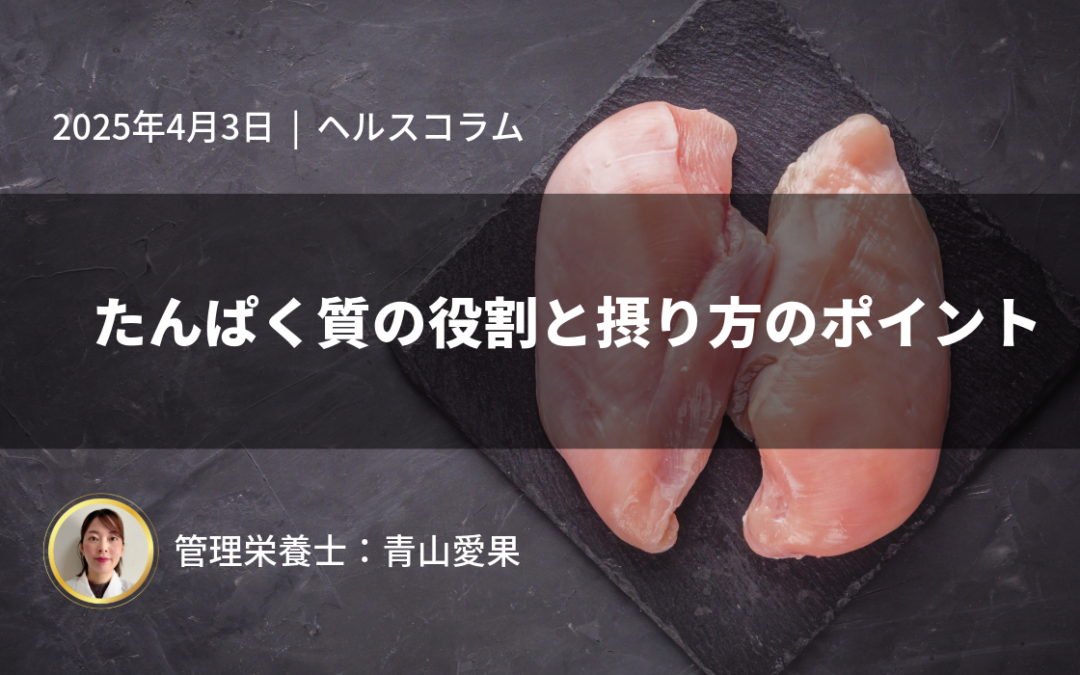この記事の著者
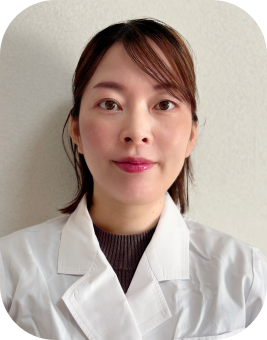
【氏名】青山愛果(管理栄養士)
【経歴】
2013年~2022年 病院管理栄養士として勤務
2024年 管理栄養士としてフリーランスとして活動
【資格・免許】
2011年3月 栄養士免許 取得
2013年5月 管理栄養士免許 取得
たんぱく質とは
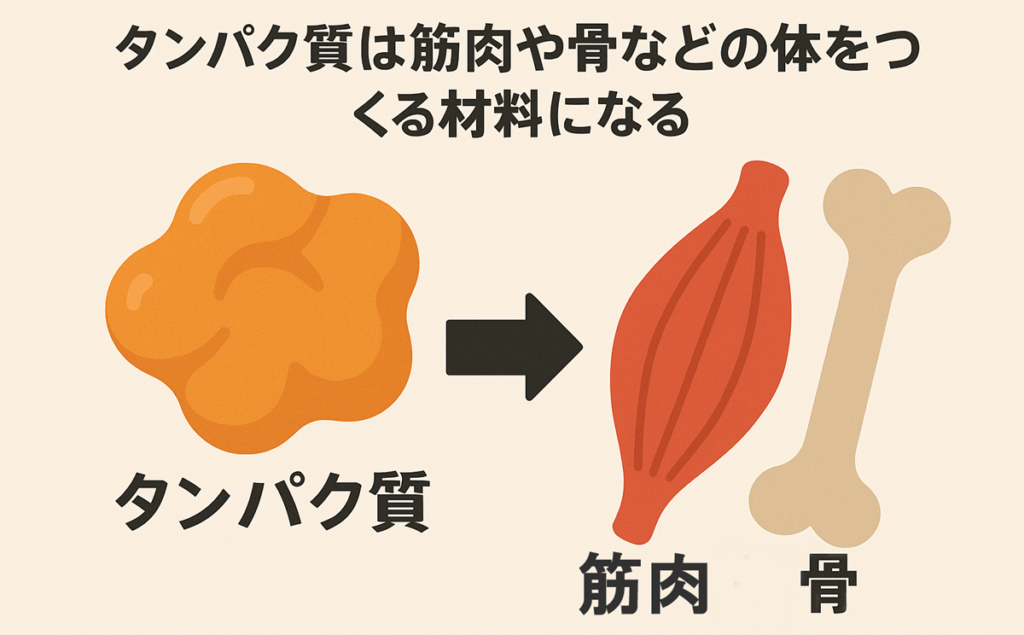
20種類のアミノ酸から出来ており、筋肉や骨などの体をつくる材料になります。
アミノ酸の中には体内で合成できない「必須アミノ酸」と呼ばれるものがあり、食事から摂る必要があります。
アミノ酸は種類によって、酵素やホルモン、免疫物質など働きがさまざまです。
筋肉を作るのに必要なイメージの強いたんぱく質ですが、多く摂れば摂るほど筋肉がつくわけではありません。
過剰なたんぱく質はエネルギー源として使われたり、体脂肪として蓄積されてしまいます。
脂質や糖質と異なり、たんぱく質はエネルギーとして使われた時に老廃物が生じます。
この老廃物を体から排出するため腎臓に負担がかかることがデメリットです。
このため、たんぱく質を摂る量は多ければ良いという訳ではありません。
また、ダイエットのために糖質や脂質からのエネルギーを制限しすぎてしまうと、たんぱく質がエネルギー源として使われてしまいます。
そのため、たんぱく質が体をつくる材料としての働きを十分得るためにも、糖質や脂質でエネルギーを十分補うことが大切です。
たんぱく質が足りなくなると、体力や筋力・筋量の低下や免疫力が落ちることがあります。
特に高齢者はたんぱく質不足の影響が大きく、加齢と重なり筋力・筋量の低下が加速されます。
毎日を元気に過ごすために、適量のたんぱく質を摂ることは大切です。
1日に摂るたんぱく質量の目安は、下記の記事をご確認ください。
▶栄養バランスの基本!エネルギー産生栄養素バランス(PFC比)の考え方について
良質なたんぱく質とは?

たんぱく質は量を十分摂るだけでなく、その質に注目することも大切です。
「良質なたんぱく質」とは、必須アミノ酸全9種類を十分含んでいることが条件となります。
これによって、体の中で効率良くたんぱく質としての働きを発揮できるのです。
必須アミノ酸のバランスを数値化したものを「アミノ酸スコア」と呼び、これが100に近いものを「良質なたんぱく質」と呼びます。
肉、魚、卵、大豆製品、乳製品は良質なたんぱく質を含む食材です。
穀類や野菜にもたんぱく質は含まれますが、これらはアミノ酸価が低く、質が良いとはいえません。
かけそばや菓子パンなどで1食を済ませると、アミノ酸価の低い食事となってしまいます。
この場合、たんぱく質は効率良く使われずエネルギー源として消費されてしまうのです。
肉そばや月見そば、卵サンドやチキンサンドなどを選び、たんぱく質を補いましょう。
毎食、肉や魚などの良質なたんぱく質を使用した主菜をとることが大切です。
たんぱく質の摂り方のポイント
良質なたんぱく質を摂った上で、更に気を付けたいポイントが2つあります。
- 肉、魚、卵、大豆、乳製品をまんべんなく取り入れる
- たんぱく質の代謝を助けるビタミンを併せて摂る
それぞれの詳しい内容を紹介します。
1. 肉、魚、卵、大豆、乳製品をまんべんなく取り入れる
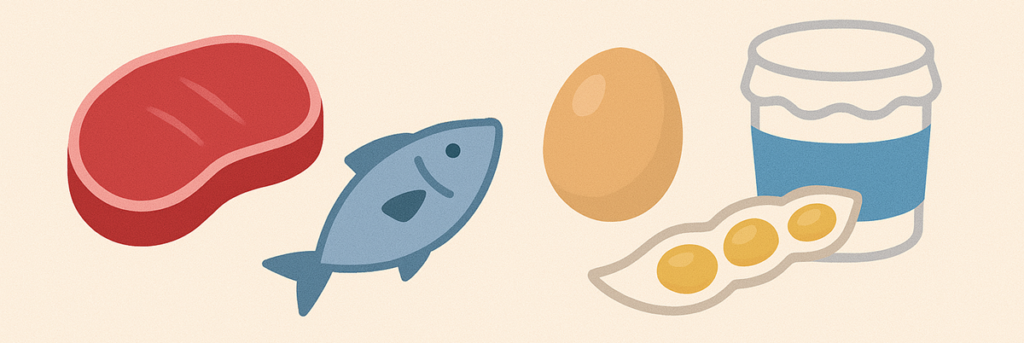
アミノ酸スコアが高いことに共通した食品でも、その他に持つ栄養素の特徴が異なります。
肉はたんぱく質量が豊富な一方で、部位によっては「飽和脂肪酸」と呼ばれる動脈硬化を進める原因となる脂質を含みます。
魚は飽和脂肪酸が少なく、青魚には中性脂肪値や高血圧の改善に役立つEPAが豊富です。
卵は肉や魚に比べてたんぱく質量は少なめですが、ビタミンやミネラルの摂取源にもなる食材です。
ただ、コレステロールを多く含むことに留意しましょう。
大豆はコレステロールゼロで食物繊維やビタミン、ミネラルも豊富に含んでいる食材ですが、肉や魚ほどたんぱく質量は多くありません。
牛乳やヨーグルトなどの乳製品は単体で1食分のたんぱく質量を補うことは難しいものの、日本人に不足しがちなカルシウムを豊富に含む貴重な食品です。
食品には多くの栄養素が含まれており、その特徴は1つ1つ異なります。
特定の食品ばかりを取り入れると、栄養素の過不足に繋がります。
幅広い食品を取り入れることで、さまざまな栄養素をまんべんなく摂れるようになるのです。
「昨日の夜は肉料理だったから、今日の夜は魚にしよう」など同じ食材ばかりが続かないように意識することをおすすめします。
2. たんぱく質の代謝を助けるビタミンを併せて摂る
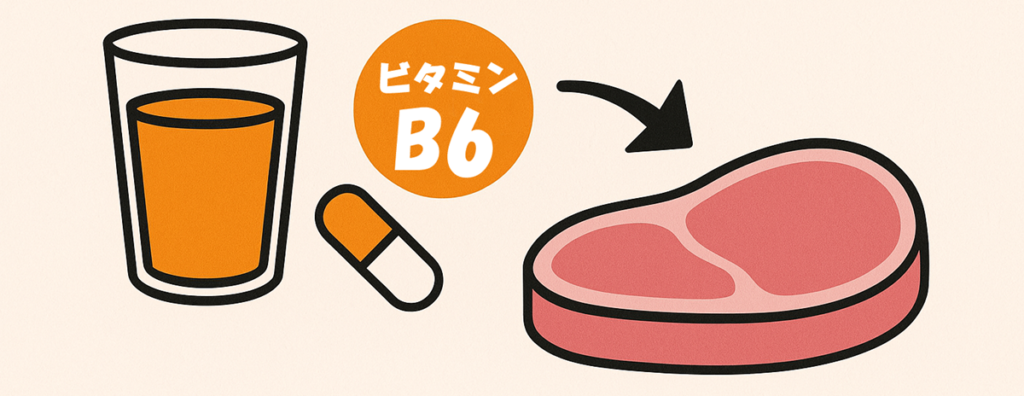
たんぱく質を体内で効率よく使うためには、代謝を助けるビタミンB6を取り入れることが大切です。
たんぱく質を多量に摂るとビタミンB6の必要量も増えるため、筋トレ中でたんぱく質を積極的に取り入れている方に注目していただきたい栄養素です。
1日に摂るビタミンB6の目標量は年齢や性別によって異なります。
18歳以上の場合、男性は1.4mg、女性は1.1mgを目安に摂りましょう。
ビタミンB6は野菜、魚、肉など幅広い食品に少量ずつ含まれています。
主食・主菜・副菜の揃った食事を普段から摂っている方は、不足しづらい栄養素です。
偏った食事になりやすい時や、たんぱく質を多く摂った際はビタミンB6の含有量が多い食品を意識的に取り入れることをおすすめします。
< ビタミンB6を豊富に含む食品 >
※食品名、食品の重量、ビタミンB6含有量の順で記載しています。
- みなみまぐろ赤身(80g) 0.86mg
- 若鶏むね肉皮無し(100g) 0.64mg
- 若鶏ささみ(100g) 0.62mg
- カツオ(80g) 0.61mg
- 輸入牛肉ランプ (100g) 0.52mg
- しろさけ(80g) 0.51mg
- まさば(80g) 0.47mg
- モロヘイヤ(100g) 0.35mg
- 和種菜花(100g) 0.26mg
- ピスタチオ(20g) 0.24mg
- しいたけ(100g) 0.21mg
たんぱく質の多い鶏むね肉やささみにビタミンB6も多く含まれているのは嬉しいポイントですね。
まとめ
筋肉や骨など私たちの体をつくるたんぱく質。
正しい知識を持つことで、たんぱく質が効率良く働けるようサポートできます。
まずは、肉、魚、卵、大豆、乳製品などの良質なたんぱく質をまんべんなく取り入れることから始めてみてください。
更にビタミンB6を併せて摂ることでたんぱく質の代謝を助けることができますよ。
参考資料
・日本人の食事摂取基準2020年版
・日本食品標準成分表八訂