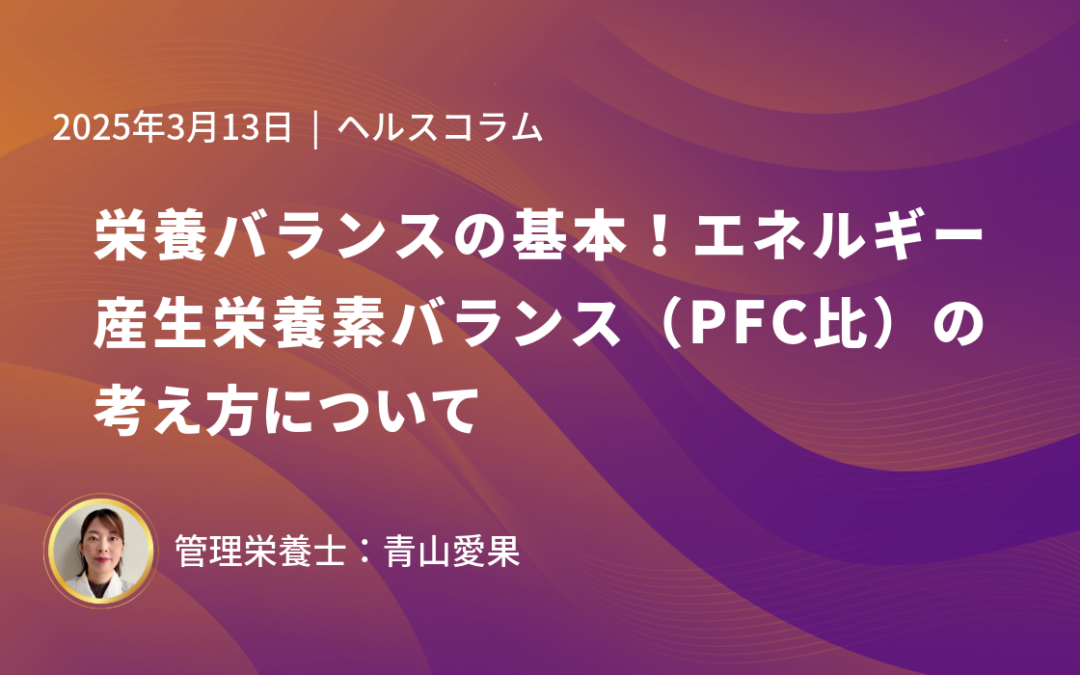この記事の著者
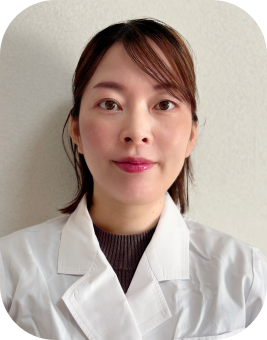
【氏名】青山愛果(管理栄養士)
【経歴】
2013年~2022年 病院管理栄養士として勤務
2024年 管理栄養士としてフリーランスとして活動
【資格・免許】
2011年3月 栄養士免許 取得
2013年5月 管理栄養士免許 取得
ダイエット中は食事からのエネルギー量が多すぎないかな?と気になるのではないでしょうか。
健康的に痩せるためには、エネルギーだけでなく栄養素のバランスに注目することが大切です。
今回は「エネルギー産生栄養素バランス」について紹介します。
エネルギー産生栄養素バランスとは
エネルギーを生み出す栄養素はたんぱく質、脂質、炭水化物の3つで、このエネルギー比率を「エネルギー産生栄養素バランス」と呼びます。
PFC比と呼ばれていたものが、2015年の食事摂取基準の改定に伴い呼び方が変わりました。
ダイエットについて調べると「糖質制限」「油は控えた方が良い」「たんぱく質は多く摂ったほうが良い」などの文言を見かけますが、具体的にどのくらいの量を摂ることが望ましいのでしょうか?
その答えがエネルギー産生栄養素バランスにあります。
生活習慣病予防においても重要であり、健康のために知っておいておきたい知識です。
まずは、エネルギー産生栄養素のエネルギー量を把握しましょう。
各栄養素1gあたりのエネルギー量は、下記のとおりです。
- たんぱく質 4kcal
- 炭水化物 4kcal
- 脂質 9kcal
目標とする量は①たんぱく質②脂質③炭水化物の順で決めていきます。
エネルギー比として示されているため、計算して重量に直す必要があります。
計算方法は下記のとおりです。
例:必要エネルギー量2000kcal たんぱく質エネルギー比15%の場合
必要エネルギー量2000kcal×(たんぱく質エネルギー比15%÷100)=300kcal
たんぱく質300kcal÷4kcal(1gあたりのエネルギー量)=75g(たんぱく質の目標量)
脂質の場合は1gあたり9kcalで計算し、炭水化物はたんぱく質と脂質を差し引いた量が目標量となるのです。
それでは、各栄養素の目標量の決め方を紹介します。
たんぱく質の目標量
たんぱく質はエネルギーを生み出す栄養素ですが、筋肉や骨をつくる材料になる栄養素でもあります。
他の栄養素から合成できないため、食品から必ず摂らなければなりません。
年齢別のたんぱく質の目標量は下記のとおりです。
- 1~49歳:13~20%
- 50~64歳:14~20%
- 65歳以上:15~20%
50歳で必要エネルギー量が2000kcalの場合、たんぱく質の目標量は70~100gとなります。
この範囲に入るように、たんぱく質の多い肉・魚・卵・大豆製品を取り入れましょう。
脂質や糖質の割合を少なくしたい方は、上限の20%までたんぱく質の割合を増やすことも可能です。
たんぱく質も摂りすぎては生活習慣病の原因になるため、上限値は超えないようにお気をつけください。
ご高齢の方は加齢によって筋肉量が減少するため、下限値が増えます。
65歳以上では1日あたり、体重1kgにつき1g以上のたんぱく質を摂ることを目標としましょう。
体重60kgの場合、たんぱく質量は1日60g以上が目標となります。
脂質の目標量
脂質は、細胞膜やホルモンの材料となり、脂溶性ビタミンの吸収を助ける働きもある大切な栄養素です。
脂質の目標量はどの年代もエネルギー比20~30%です。
必要エネルギー量が2000kcalの場合、44~67gが目標量の範囲となります。
脂質は調理油以外にも、肉・魚・卵など食品自体に含まれています。
不足することは少なく、過剰に摂っていることが多い栄養素であるため、あえて調理油を足す必要はありません。
たんぱく質の多い食品である肉や魚、卵、大豆製品を意識的に摂れていれば、脂質も補給できます。
特にダイエット中の方は揚げ物などの油を多量に使った料理は控えましょう。
例えば、豚肉を揚げてから野菜と炒め合わせる酢豚は1品に43gの油が含まれます。
これだけで1日分の脂質を摂ることになってしまうのです。
脂質の摂りすぎが気になる方は、「蒸す」「網焼き」「茹でる」調理法のメニューを選ぶとよいでしょう。
炭水化物の目標量
炭水化物には「糖質」と「食物繊維」が含まれています。
主に糖質がエネルギー源として利用され、体内で「ブドウ糖」の形でエネルギー源となります。
脳や赤血球などブドウ糖しかエネルギー源として利用できない組織があるため、私たちが生きていく上で欠かせない栄養素です。
炭水化物の目標量は、必要エネルギー量からたんぱく質と脂質を差し引いた値になり、50~65%の範囲となります。
必要エネルギー量が2000kcalでたんぱく質20%、脂質25%の場合、炭水化物は55%となります。
重量に直すと、たんぱく質100g、脂質56g、炭水化物275gです。
全体のエネルギーのうち、半分を炭水化物で摂るイメージになります。
糖質を控えたいと考えて、主食を抜くのは要注意です。
ご飯やパン、麺などの主食には糖質だけでなく食物繊維やビタミンも含まれます。
主食を減らしすぎると空腹感が大きくなり、間食が増えることも。
炭水化物は主食となるご飯やパンの他に、芋類、かぼちゃ、とうもろこしなどの野菜、揚げ物の衣、餃子や春巻きの皮、お菓子やジュース、アイスなど様々な食品に含まれています。
まずは肥満や血糖値の急上昇の原因になるジュース・お菓子・アイスなどの嗜好品から見直してみましょう。
まとめ
エネルギー産生栄養素のバランスを整えることは、健康的にダイエットする上で重要です。
自身に合ったたんぱく質、脂質、炭水化物の量を知ることで、食事の適量が掴めるようになりますよ。