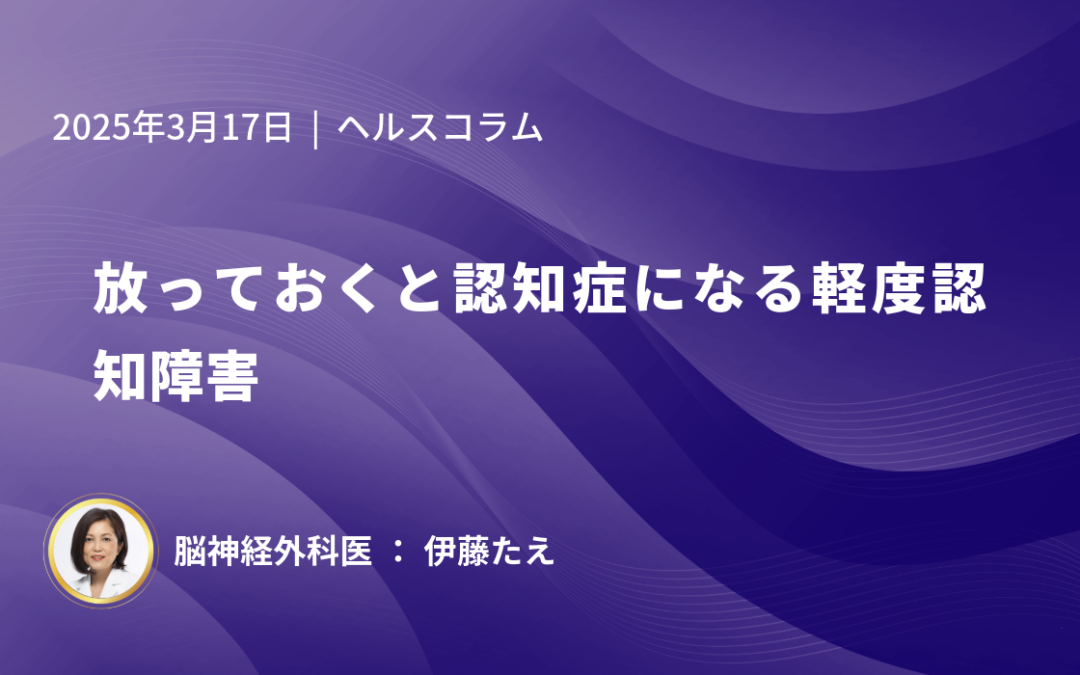この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)
【経歴】
2004年3月 浜松医科大学医学部卒業
2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修
2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局
2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務
2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務
2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務
2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科
菅原クリニック東京脳ドック 院長
【専門】
日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医
【資格・免許】
医師免許
増え続けている認知症と軽度認知障害
少子高齢化といわれて久しいですが、高齢者の割合はますます上昇しています。人口の高齢化にともない、やはり認知症になる方も増えています。
認知症とともに増えているのが、軽度認知障害です。英語表記のMild Cognitive Impairmentの頭文字をとり、MCIと呼ばれることも多いです。MCIは「認知症予備軍」の段階といえます。
MCIに、いち早く気づき、対策することで、認知症に移行するのを止められることもあります。そこで、今回はMCIについて、解説していきます。
認知症について
認知症予備軍であるMCIのお話の前に、認知症について簡単に説明しておきます。
2022年の認知症患者数は、約443万人と推計されています。これは、高齢者の約8人に1人が認知症を患っていることになります。
ちなみに、MCIの高齢者数は558.5万人と推計されています。
認知症とは、いろいろな原因により、脳の機能が正常に機能しなくなってしまった状態です。認知機能が低下し、日常生活に支障をきたしてしまいます。
認知機能とは、記憶する、考える、判断するなどの能力のことです。
認知症の症状で最も早く気づきやすいのは、記憶力の低下、つまり物忘れです。進行とともに、歩行や移動、食事といった基本的な身体動作も、うまくできなくなってしまいます。
認知症の種類
認知症には様々な疾患が含まれています。
その中でも、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症、前頭側頭型認知症などが代表的な疾患です。
アルツハイマー型認知症
認知症のうち、全体の約6〜7割を占めます。記憶をつかさどる海馬の萎縮から始まるため、もの忘れなどの記憶障害が起きます。
レビー小体型認知症
脳細胞のなかに、レビー小体と呼ばれる特殊なたんぱく質が留まることが特徴です。
アルツハイマー型認知症に似ていますが、存在しないものが見える幻視という症状や、パーキンソン病に似た症状を伴います。
脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血などの脳卒中により、脳の機能が障害されても、認知症になることがあります。障害部位によりますが、身体麻痺、言語障害になることもあります。
前頭側頭型認知症
前頭葉や側頭葉の変性・萎縮で引き起こされる認知症です。理性が低下したり、同じ行動を繰り返したりすることもあります。
その他
正常圧水頭症やアルコール依存症、うつ病、甲状腺機能低下症などが認知機能の低下を引き起こすことがあります。
これらに関しては、原因となる病気が改善することで認知機能も正常に戻るケースもあります。
治療薬について
アルツハイマー型認知症に対しては、アセチルコリン(脳内の神経伝達物質)を分解する酵素の働きを抑える薬が以前から使われています。
2023年12月には、認知症の原因となる脳内に溜まったアミロイドβというタンパク質を除去する薬が発売されました。
しかし、いずれも、症状の進行抑制に効果を期待できますが、認知症が治るわけではありません。
認知症予備軍(MCI)とは
MCIとは、ご本人やご家族に認知機能低下の自覚があるものの、日常生活は問題なく送ることができている状態のことです。
しかし、行きなれている場所に行ったり、使いなれた機械は使えても、新しい場所や機械は苦手になります。
日常生活も、どうにか送れるものの、テキパキと行うことは難しくなっています。
MCIの状態から、さらに日常生活に支障が出始めると、認知症の状態にあると判断されます。
MCIは、健常な状態と認知症の中間の状態であり、認知症へ進行するだけでなく、健常な状態にも戻れる可能性があります。
MCIのうち、年間で約10〜15%が認知症に進行すると言われています。一方で、適切な生活習慣や治療で、進行を抑えることができることもあります。
MCIでは、記憶力に軽度の低下がみられる場合が多く認められます。
以前と比べてもの忘れが多いと感じる場合、ご家族や周りの人からもの忘れを指摘されることが多くなった人はもの忘れ外来への受診をおすすめします。
MCIが疑われる症状のチェックリスト
■もの忘れをするようになった
■物事を覚えるのに時間がかかるようになった
■料理の腕が落ちた、味付けが変わった
■掃除や洗濯といった家事がテキパキとこなせない
■時間・場所の把握が苦手になった
■薬の管理ができない
■気分が沈むことが多くなった
■頑固になった、怒りっぽくなった
約束を忘れたり、同じ話や質問を何度もしたりするようになります。コンロの火のつけっぱなしや、なくし物が多くなります。
複雑なことや、手間がかかることを避けようとします。手の込んだ料理を作らなくなり、同じものばかり作ったり、味付けも変わってしまうことがあります。
感情表現が乏しくなったり、気持ちが沈むことが多くなったり、あるいは逆に怒りっぽくなることもあります。
運動や健康的な食生活がMCI改善のカギ
MCIを予防したり、改善する上でもっとも効果的なのは、生活習慣病にならないことです。
生活習慣病は、食事や運動などの生活習慣が原因となる病気です。糖尿病や高血圧、脂質異常症、肥満などです。
これらは認知症とも深くかかわっていることが報告されています。
生活習慣病の予防は、若い健康なうちから始めなくてはいけません。遅くとも40代から対策を始めることをおすすめします。
齢者を対象とした調査では、定期的な運動が、認知症リスクを抑えることがわかりました。
運動中に計算したり、しりとりをするなど脳に負荷をかけると、より効果的だとされていいます。
運動課題・認知課題を同時に行い、心身の機能を高めるトレーニングを「コグニサイズ」と呼びます。
社会活動への参加も、MCIや認知症の予防に有効とされています。
退職時の年齢が1歳高くなるごとに認知症リスクは3%下がると言われています。
地域コミュニティへの参加も、生活機能低下に歯止めをかけます。読書やパズル、楽器の演奏といった手先や頭を使う活動、ボランティアへ参加しても良いでしょう。
MCIの高齢者は栄養不良の割合が高く、認知症発症前に体重低下などが報告されています。
食べ過ぎはよくありませんが、バランスの良い食事を適量とることが大切です。
MCIや認知症が疑われた時には
認知機能の低下を感じるのはMCIや認知症だけではありません。他の病気が原因の可能性もありますので、まずは医療機関に相談しましょう。
かかりつけ医や、神経内科や脳神経外科、あるいは、認知症を早期に発見・治療するための「もの忘れ外来」にかかるのもよいでしょう。
高齢者の健康面や生活全般をケアする「地域包括支援センター」でも、認知症に関する相談を受け付けています。
状況に応じて、適切なサービスにつなげてくれます。相談先がわからない場合は、電話などで行政に連絡すれば、同じく必要な保健医療サービスを紹介してくれます。
親に疑いがある場合、子どもから診療をすすめても、症状を否定して、聞いてもらえないこともあります。
しかし、放置するのはよくありませんので、ゆっくり説得してください。認知症といわずに、脳の健康診断に行こうと勧めてみるのもよいでしょう。
親と離れて暮らしている場合は、症状に気づくのが遅れがちです。定期的に連絡を取って、様子をうかがうようにしましょう。
近所に頼れる人が住んでいるなら、調子がおかしいと感じたときには、連絡をもらえるようにしておくのが良いでしょう。
参考
令和6年版 高齢社会白書
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/zenbun/pdf/1s2s_02.pdf
あたまとからだを元気にする MCIハンドブック
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/kibou_00007.html