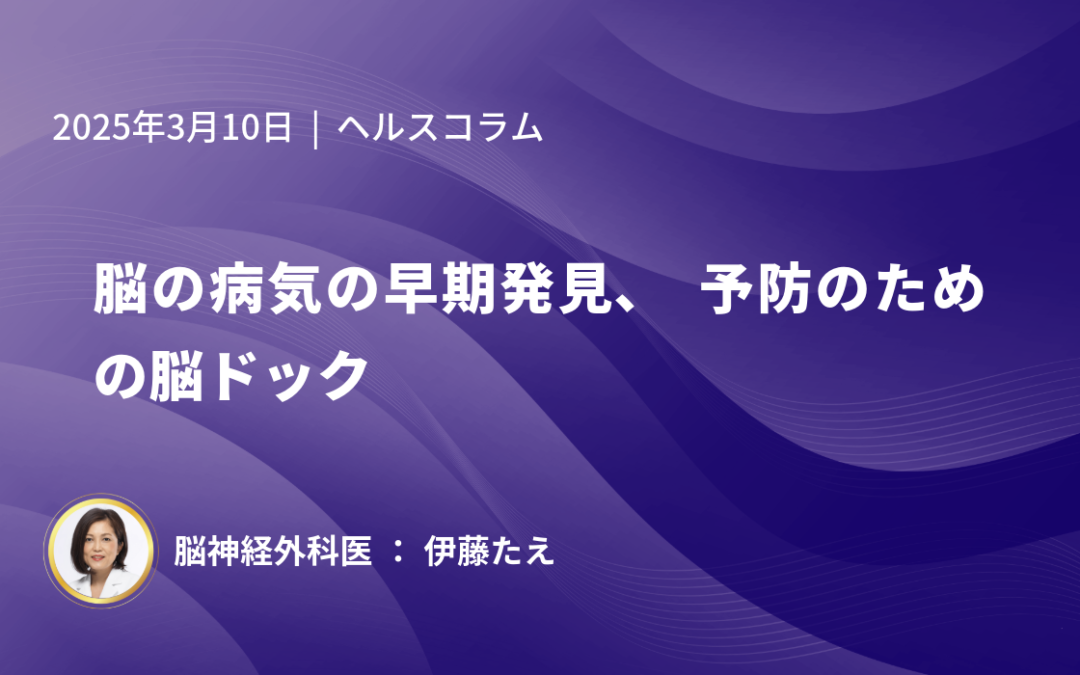この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)
【経歴】
2004年3月 浜松医科大学医学部卒業
2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修
2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局
2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務
2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務
2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務
2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科
菅原クリニック東京脳ドック 院長
【専門】
日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医
【資格・免許】
医師免許
健康診断や人間ドックを定期的に受けている人は多いと思います。しかし、脳ドックに関しては、まだまだ受診率が低い水準にとどまっています。
人間ドックのオプションに、脳ドックがついている場合もありますが、通常は脳の検査は含まれません。
昨今、脳ドックの認知度は高まってきていますが、20代、30代では脳ドックというもの自体を知らない人も多いようです。
50代以上になると、脳ドックの受診率が、徐々に上昇する傾向がありますが、脳ドックの受診率は16.0%程度という調査結果もあります。
脳ドックの目的
脳の病気は初期の段階では自覚症状が出にくいこともあります。脳ドックの目的は早期発見と予防です。脳の病気に関するリスクの評価も含まれます。
つまり、脳ドックは、みなさんの健康福祉に貢献することを目的としたものなのです。
なぜ、脳の健康が重要かというと、要介護状態の原因は、脳による病気が圧倒的に多いからです。
令和元年の高齢者白書によると、要介護の原因として、男性では24.5%を脳卒中が、女性では19.9%を認知症が占めています。
それぞれ最も多い要介護の原因疾患となっているのです。
高齢化が著しい日本の状況を鑑みると、脳卒中と認知症の予防はとても重要です。
健康寿命を延ばして、みなさんが長く元気に活躍できる社会を目指す必要があります。
脳ドックは、症状のない方が、早期発見、予防のために受診します
以前は、脳ドックは、脳動脈瘤や、無症候性脳梗塞(かくれ脳梗塞)、動脈硬化の発見や、脳卒中の予防を目的として受診されることが多かったです。
しかし、最近では、もの忘れを心配して受診される方も増えてきました。
ここで一つ知っていただきたいのですが、脳ドックは、症状がない方が受診されることが前提です。
もし、体の一部が動きにくいとか、頭痛がひどい、あるいは物忘れをするなど、明らかに異常を感じる症状がある方は、普通に保険診療で脳神経外科などを受診しましょう。
脳ドックは、症状が出ていない脳梗塞や脳出血、血管狭窄を早期に発見することができます。脳ドックで発見された血管病変の危険因子を、取り除けるようにしていきます。
具体的には、生活習慣に介入して2次予防を行うことで、病気の進展を防ぐことができます。
どのような方が、特に脳ドックを受けておいたほうがいいかというと、中高年の方や、脂質異常症、高血圧、糖尿病のある方たちがあげられます。
また、肥満気味の方や喫煙される方も、必要性は高まります。若くても、脳卒中や認知症の家族歴のある方も、一度受けておいたほうが良いでしょう。
脳ドックの内容
脳ドックはクリニックによって、コースがいくつかに分かれている場合があります。
基本となるのは頭部MRI、MRAです。その他に頚部(けいぶ)の超音波検査(エコー検査)が含まれていることも多いです。
採血や心電図は、他の検診や人間ドックで行ってない場合は、まとめて行うのも良いでしょう。
脳に関係する病気の診断や、早期発見、リスクの評価を目的に行われます。
頭部MRI、MRA
【MRI】
MRIはMagnetic Resonance Imagingの略で、磁気共鳴画像法といいます。とても強い磁場と電波を使って、体の断面を撮影する検査です。
MRIの原理は、非常に難解なのですが、簡単に説明すると、MRI装置が、強力な磁場を発生させ、体内の水素原子に作用し、その現象を電気信号に変換して画像にします。
【MRA】
MRAはMagnetic Resonance Angiographyの略です。MRIと同じ原理を利用しますが、血管の中を流れる血液の流れを強調して画像化します。
検査中は大きな磁石のトンネルの中に入らなければならず、機械から大きな音が出ますので、苦手な方もいます。しかし、CTとは違って放射線を使いませんので、被爆のリスクはありません。
体内に医療金属を埋め込んでいる方は、MRIを受けられない場合があります。特に心臓ペースメーカーに対応している施設は少ないです。タトゥーも難しいことがあります。
閉所恐怖症の方は、安定剤を内服や注射をして行うこともありますが、事前に検査機関に相談が必要です。閉塞感を感じにくいオープンMRIを選択するという方法もあります。
最近マグネットネイルをつけている方が増えてきていますが、マグネットネイルは鉄粉を含むので、MRIは受けられません。
頚動脈エコー
頚動脈は、脳に血液を供給する首の血管です。
この血管の状態を調べるため、超音波を用いて検査します。血管の構造や血流を画像化し、動脈硬化の有無や程度、血管の狭窄などを確認することができます。
首に超音波を当てるだけですので、痛みや放射線被ばくの心配はありません。検査時間は20分程度です。
動脈硬化が進行すると、血管壁の厚みが増えます。コレステロールなどが溜まってできた塊(プラーク)の有無を評価したり、血管の狭窄率を測定したりします。
大きなプラークや、不安定なプラークを認めたり、血管の狭窄が強い場合は、脳梗塞になるリスクが高くなります。
脳ドックで見つかりやすい病気
無症候性脳梗塞
MRIの画像上、脳梗塞の所見があり、その病変にあてはまる症状がないものを言います。かくれ脳梗塞と呼ばれることもあります。
脳梗塞になっても症状がないので、日常生活を普通に送っています。脳ドックを受けて、はじめて分かるような病変です。
一般的には50代以降で多く見られるようになり、珍しいものではありませんが、将来の脳卒中や認知症の危険因子とされています。
生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)や喫煙などのリスクファクターを持つ人は、より若い年齢でも無症候性脳梗塞を発症する可能性があります。
通常は、リスクファクターを取り除けるように、生活習慣の改善を目指します。
治療する必要がある場合は、血液をサラサラにする作用のある抗血小板を使用することもあります。
脳微小出血
脳の細い血管が破れて、ごく少量の出血が起こる状態です。ほとんどの場合、自覚症状はありませんので、脳ドックなどで偶然発見されることが多いです。
年齢を重ねるごとに発生頻度が高まります。高血圧も、脳微小出血の原因になります。
脳微小出血があると、将来的に脳卒中や認知症を発症するリスクが高まることが報告されています。
脳微小出血が見つかった場合は、血圧のコントロールをしっかりしていきましょう。
脳動脈瘤
未破裂脳動脈瘤は、30歳以上の成人において約3%の頻度で認められます。
特に高血圧、喫煙、脳卒中の家族歴がある方は注意を要すると言われています。
動脈瘤が破裂するとくも膜下出血になりますが、破裂率は決して高くありません。動脈瘤の場所や大きさで破裂する率が変わってきます。
破裂率は高くありませんが、血圧のコントロールや過度の飲酒を控えるなどの対策は必要です。
喫煙も破裂のリスクを増大させますので、喫煙している方は禁煙しましょう。
脳腫瘍
脳ドックで見つかりやすい脳腫瘍は、髄膜腫や下垂体腺腫など良性のものが多いです。
それぞれの腫瘍によって方針が異なります。腫瘍のできている場所や大きさによって、今後の方針を検討していきます。
内頚動脈狭窄症
内頚動脈の狭窄は、将来的に脳梗塞となる可能性が高いですが、内服治療により予防できます。
内頚動脈に狭窄が見つかった場合は、他の血管も動脈硬化になっている可能性が高いです。
心筋梗塞や下肢の動脈閉塞末の危険も高いので、内科的な管理が必要になります。
内頚動脈の狭窄が強い場合、外科的治療を要する場合がありますので、担当医とよく相談してください。
脳ドックとの向き合い方
脳ドックで異常が見つかっても、すぐに外科的な治療を要するものは少ないです。生活習慣の改善や、画像による経過観察となる場合が多いです。
薬の内服を開始することもあります。担当医とよく話し合いましょう。
頭部MRIでは、海馬などの萎縮も分かるため、認知症になるリスクもある程度、画像から推測できます。
最近は、脳ドックの検査項目に、認知機能の精密検査を盛り込んでいる施設も増えてきています。認知症が心配な方は、そのような施設を選ぶとよいでしょう。
最近はスピーディーに脳ドックを受けられる施設もありますが、対面での説明がなく、質問ができない脳ドックもありますので、自分に合った脳ドックの施設を選びましょう。
参考
日本脳ドック学会
https://jbds.jp/