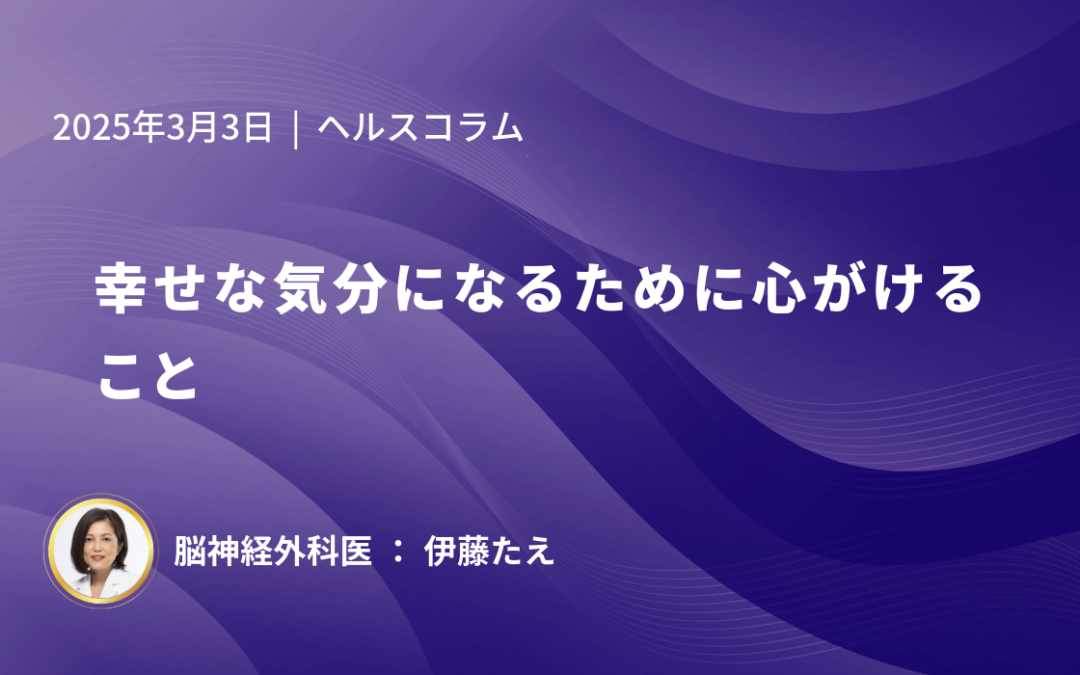この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)
【経歴】
2004年3月 浜松医科大学医学部卒業
2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修
2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局
2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務
2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務
2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務
2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科
菅原クリニック東京脳ドック 院長
【専門】
日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医
【資格・免許】
医師免許
幸せとは
幸せになりたい、それは誰もが抱く望みだと思います。
では、改めて、幸せとは何かと考えたとき、どのように考えますか?
家族が健康で仲良く暮らせているとき、仕事のプロジェクトが成功したとき、片思いが実を結んだとき、あるいは目標額の貯金ができたときなどの状況が思い浮かぶかもしれません。
しかし、本来、幸せとは脳が感じた状態であり、周囲の環境で決定できるものではありません。では、幸せな気持ちを感じるとはどういうことなのか、今日はお話ししていきたいと思います。
その仕組みがわかれば、今よりもっと幸せな気分で生活できるかもしれません
幸せを感じる場所はどこなのか
幸せや満足感を感じると活発に働く脳の重要な場所をご紹介していきます。
ただ、幸せを感じる脳の部位は、未だ十分解明されておらず、今後も新しい見解が出てくる可能性もあります。
前頭前野
まずは前頭前野(ぜんとうぜんや)という額の後ろにある脳の部分です。
人間はこの場所が他の動物より、大きく発達しています。脳の中で進化的に最も新しく、高度に進化した領域です。
感情の調整や意思決定に関与し、ポジティブな感情を促進する役割があります。
側坐核
側坐核(そくざかく)は、大脳基底核の一部で、前頭前野のすぐ後ろに位置しています。
欲求や快感に関わる部位です。
美味しいものを食べた時や、異性から褒められた時などに活発になります。快感や喜びを得るために、行動を促す役割も担っています。
扁桃体
扁桃体(へんとうたい)も、幸せと密接に関連しています。
扁桃体は、脳の内側に位置する小さな器官です。
強い感情を伴う出来事(怖い体験や喜びの瞬間)は、扁桃体の働きによって記憶として強く残ります。
海馬
記憶の形成で有名な海馬も、幸せを感じるのに重要な器官です。
ポジティブな経験を記憶することで、喜びを思い出したり、幸福感を維持したりすることができます。
報酬系
快感や満足感を感じさせる神経回路の集まりである脳内報酬系(ほうしゅうけい)も重要な働きをします。
脳内報酬系は記憶、情動、意思決定などを司る他の神経系と連携して、人間や動物の行動を調節しています
報酬系は、薬物依存やギャンブル依存などの依存症とも深く関わっています。
SNSの「いいね!」も、報酬系を刺激することが知られています。投稿に「いいね!」をもらうと、快感を感じます。快感を感じることによって、もっと「いいね!」が欲しくなり、投稿を繰り返すようになり、度が過ぎるとSNS依存状態になります。
このように報酬系は、幸せな気分になったり、もっとがんばろうという気持ちを持てるという大切な働きの影に、負の側面も持ち合わせているので、注意が必要です。
幸せを感じる神経伝達物質やホルモンを増やしましょう
つぎに、幸せに大きく影響する神経伝達物質やホルモンについて説明していきます。
これらは日常生活の工夫によって、分泌を促すことも可能です。
「快楽ホルモン」ドーパミン
幸せな感情になるホルモンといって思い浮かぶのがドーパミンではないでしょうか。ドーパミンは「快楽ホルモン」とも呼ばれ、うれしいことや気持ちのいいことを感じる際に分泌されます。
新しい経験や目標達成、趣味に没頭することでドーパミンが分泌され、幸福感を高めることができます。
ドーパミンを増やす生活
睡眠不足はドーパミン受容体の機能を低下させ、ドーパミンの効果を減少させてしまいます。質の良い睡眠をとることが大切です。
運動によりドーパミンの分泌が促され、特に有酸素運動や筋肉トレーニングが良いといわれています。
慢性的なストレスは脳内ホルモンのバランスを崩し、ドーパミンの生成を妨げることがあります。ストレス管理が大切なので、息抜きの趣味や、瞑想や深呼吸で気分を整えましょう。
目標達成時にもドーパミンが分泌されるので、達成しやすい小さな目標を設定し、目標達成時にドーパミンが分泌されるようにすると、モチベーションが上がります。
ドーパミンを増やすためには、食生活も重要です。ドーパミンはアミノ酸の一種であるチロシンという物質から合成されるため、チロシンを多く含む食品を食べるように心がけましょう。
チロシンを多く含む食品としては、魚、鶏肉、大豆製品、卵、乳製品などです。
ドーパミンの生成を助けると言われているオメガ3脂肪酸も摂取するようにしましょう。EPAやDHAが脳に良いと聞いたことがあるかもしれませんが、それらはオメガ3脂肪酸に属します。
「幸せホルモン」セロトニン
セロトニンは、気分を安定させる役割を持つ神経伝達物質です。
落ち込んだ気分の時には、セロトニンが不足していると聞いたことがある方もいるかもしれません。運動や日光浴、バランスの取れた食事がセロトニンの分泌を促進し、心の安定や幸福感をもたらします。
セロトニンは、ストレスを感じやすい現代社会において、セロトニンの不安や緊張を和らげる安定作用は非常に重要です。
喜びや快感を感じやすくする働きがあるため、「幸せホルモン」と呼ばれることもあります。
セロトニンを増やす生活
セロトニンを増やすためには食事が重要です。
セロトニンは必須アミノ酸であるトリプトファンから作られます。必須アミノ酸は体内では合成できず、食事から摂る必要があります。トリプトファンを多く含む食べ物を積極的に摂りましょう。
トリプトファンは、肉類(特に鶏肉)、赤みの魚、卵、乳製品、大豆製品、ナッツ、バナナなどに豊富に含まれています。
セロトニンの合成にビタミンB6、B12、葉酸などが必要なため、これらのビタミンを含む食品(緑葉野菜、豆類、全粒穀物、肉類など)も意識的に摂取することが大切です。
ドーパミンと同様に、セロトニンも運動で分泌が促進されます。特に有酸素運動(ジョギング、ウォーキング、サイクリングなど)が効果的です。
睡眠は脳の健康にとって重要であり、睡眠不足はセロトニン受容体の機能を低下させてしまいます。質の良い睡眠を確保することでセロトニンのバランスを保つことができます。
日光を浴びることで、セロトニンの生成が促進されます。特に朝の光を浴びることが効果的です。
また、ストレス管理も重要です。ストレスの強い状況下ではセロトニン分泌が抑制されてしまいます。リラックスできるような環境を整えましょう。深呼吸やヨガ、瞑想をすることもいいでしょう。
「愛情ホルモン」オキシトシン
オキシトシンも幸せに大きくかかわります。
オキシトシンは「愛情ホルモン」と呼ばれることもあります。親密な関係や絆を深める際に分泌されます。人との触れ合いや信頼関係を築くことでオキシトシンが増え、幸福感が高まります。
オキシトシンは、ストレスを軽減し、リラックス効果をもたらします。他者との信頼関係を築き、協調性を高めるという、人間関係を円滑にする作用もあります。
オキシトシンを増やす生活
ハグや手をつなぐなどの身体的接触は、オキシトシンの分泌を促進します。ペットとの触れ合いも同様の効果があるとされています。
ストレスはオキシトシンの分泌に悪影響を与えるため、ストレスを避ける生活を心がけましょう。瞑想、深呼吸、ヨガなどのリラクゼーションを取り入れてみましょう。
定期的な運動は、オキシトシンの分泌も促進することが示されています。有酸素運動やストレッチなどが効果的です。
食事に関しては、上述のホルモンのように特定の食品がオキシトシンの分泌に直接的に影響を与えるかどうかは明確ではありません。しかし、全体的に健康的な食事は、身体のホルモンバランスを整えるのに役立つと考えられています。
まとめ
幸せを感じる脳の場所や、幸せをもたらすホルモンなどについてお話させていただきました。
食事や生活習慣、睡眠も影響を及ぼすため、できるだけ幸せを感じやすくするような生活を心がけると良いでしょう。