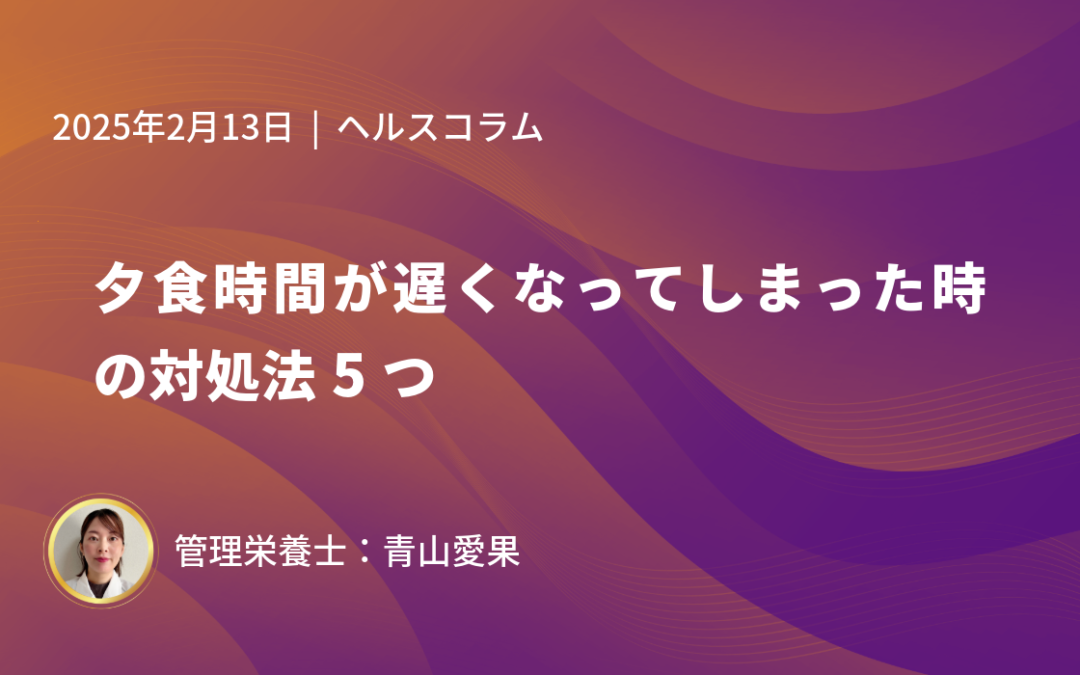この記事の著者
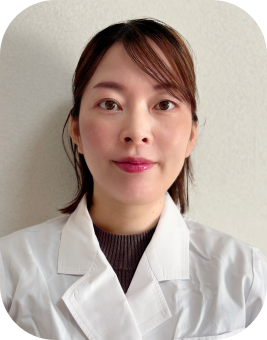
【氏名】青山愛果(管理栄養士)
【経歴】
2013年~2022年 病院管理栄養士として勤務
2024年 管理栄養士としてフリーランスとして活動
【資格・免許】
2011年3月 栄養士免許 取得
2013年5月 管理栄養士免許 取得
就寝時間の直前に食べると太りやすくなると分かっていても、遅くまで仕事をしていると難しいこともありますよね。
今回は夕食の時間が遅くなってしまう場合の対処法を紹介します。
夕食をとる理想の時間とその理由
夕食は就寝2~3時間前までに済ませることが理想です。
活動している日中は食事から摂ったエネルギーを消費できますが、夕食後すぐに就寝してしまうとエネルギーが消費しきれません。
エネルギー代謝できなかった糖質や脂質は脂肪として体に蓄えられてしまい、それが肥満の原因となるのです。
夕食が遅くなる場合の対処法5つ
やむを得ず夕食時間が遅くなる場合でも、太りにくくする対処法があるのでご安心ください。
「低カロリーであること」と「消化吸収のしやすさ」がポイントとなります。
具体的な対処法は下記の5つです。
- 夕食を2回に分けて食べる
- 野菜を取り入れる
- 脂質の少ないメニューを選ぶ
- 食べる量を腹八分目までに抑える
- よく噛んで食べる
それぞれの具体的な方法を説明します。
1. 夕食を2回に分けて食べる
仕事の合間に休憩をとれる方におすすめの方法です。
夜間に強い空腹感を感じると、つい食べ過ぎてしまうこともありますよね。
1食分の食事を夕方と夜間の2回に分けて食べることで、強い空腹感を抑えることができます。
それぞれの時間に食べるメニュー選びがポイントです。
夕方にはおにぎりやサンドイッチ、バナナなどの糖質中心のメニューを食べておきます。
駅の立ち食い蕎麦やうどんも良いでしょう。
そして、夜間にはたんぱく質と野菜を中心にしたメニューで食事をとります。
糖質摂取後に活動する時間が残されるため、エネルギーとして消費できることがこの方法の特長です。
不足しがちな栄養素であるたんぱく質と食物繊維・ビタミン・ミネラルは、食事時間を十分にとれる夜間に補給しましょう。
2. 野菜を取り入れる
野菜に含まれる食物繊維には、余分な糖や脂質・コレステロールを体の外に出してくれる働きがあります。
ダイエットはもちろん、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病予防には欠かせない栄養素です。
野菜は噛み応えがあって食べた時の満足感があり、空腹感をカバーできることもメリットといえます。
特におすすめの食材がブロッコリーです。
1/4株(90g)に4.6gの食物繊維が含まれており、その量は野菜の中でもトップクラス。
スーパーやコンビニで冷凍食品としても手に入れられるため、常備しておくと便利です。
3. 脂質の少ないメニューを選ぶ
脂質は消化に時間がかかり、高カロリーな栄養素です。
夜遅い時間に多く摂ることでカロリーオーバーになることに加え、消化吸収に負担がかかってしまいます。
お惣菜を買って食べる方は、揚げ物に目が留まることが多いかもしれません。
唐揚げやフライよりも、焼き鳥や焼き魚、煮物を選ぶと脂質量を抑えられます。
手軽に食べられるカレーや牛丼などの1品料理も脂質が多くなりがちです。
肉や魚を焼く、蒸す、煮る調理法のメニューを選ぶと良いでしょう。
4. 食べる量を腹八分目までに抑える
遅い夕食でのドカ食いは太りやすくなることはもちろん、胃腸に負担をかけるため避けたいものです。
自分が食べすぎかどうかは、食べている時の満腹感によってある程度判断することができます。
遅い夕食は満腹になるまで食べず、「もっと食べたいな」と思う程度で抑えましょう。
カロリー計算をするよりも簡単な方法なので、是非お試しいただきたいです。
5. よく噛んで食べる
よく噛んで食べることは、満腹感を感じられることと消化吸収を促すことの2つの利点があります。
早食いは十分な食事量をとっていても満足感を感じられず、食べ過ぎになりがち。
また、よく噛んで唾液の分泌を促すことは、消化を助けることにつながります。
歯で食べ物を細かくすることも消化吸収しやすくするためには大切です。
肉や魚は大きめにカットされたものにする、ゴボウやレンコンなどの硬い食材を取り入れるなどの方法で自然と噛む回数を増やすこともできますよ。
遅い時間の食事は特に意識してゆっくり召し上がって下さい。
まとめ
夜遅くまで働いた後は、疲労困憊で食事の内容を考えることも大変ですよね。
「今日は帰りが遅くなりそうだな」という日があらかじめ分かる場合は、事前にメニューを決めておくことをおすすめします。
5つの対処法の中からご自身にできそうなことを是非お試しください。
参考資料
e-ヘルスネット 交代制勤務者の食生活に関する留意点
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-04-004.html