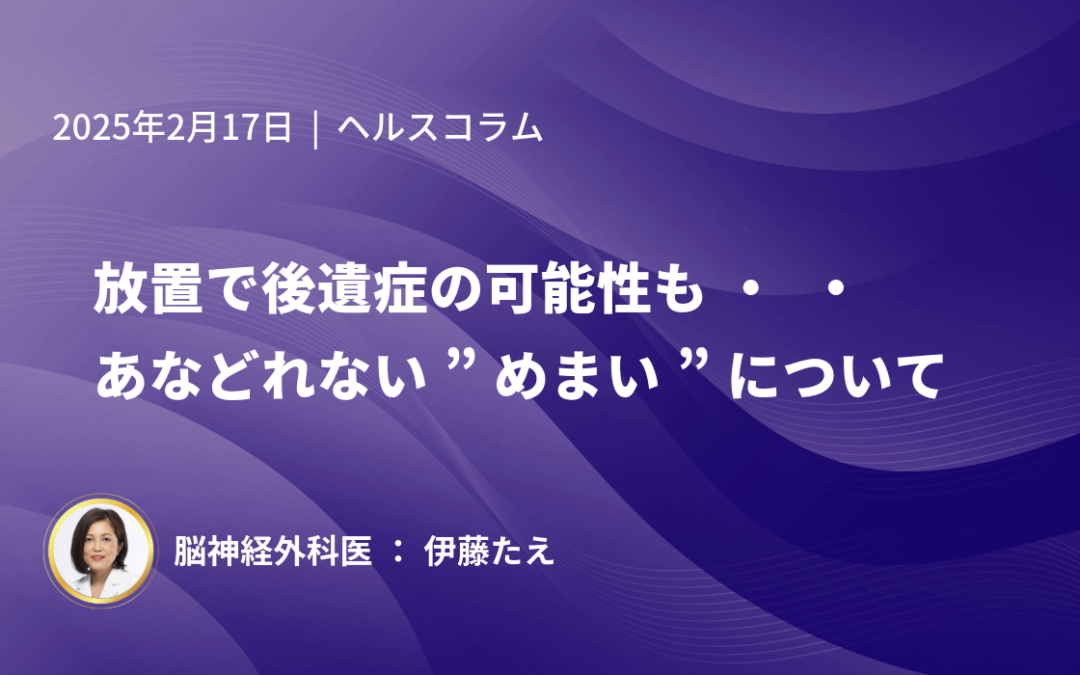この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)
【経歴】
2004年3月 浜松医科大学医学部卒業
2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修
2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局
2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務
2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務
2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務
2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科
菅原クリニック東京脳ドック 院長
【専門】
日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医
【資格・免許】
医師免許
私は普段、脳神経外科クリニックで外来診療を行っていますが、めまいの訴えで受診される方は多くいらっしゃいます。
一言でめまいと言っても、症状も原因もさまざまです。
めまいの性質やめまいが起こる時の状況などを細かく伺います。麻痺や言葉の障害がないかなどの神経所見をとって、必要に応じて画像検査も行い、診断、治療に結び付けていきます。
めまいを放置したり、めまいの自己診断をおこなうことは、めまいの治りが遅くなる原因になりかねません。後遺症を残してしまう可能性さえあります。
ぐるぐる回転するめまいやふわっとするめまい
まずは、めまいとはどのような状態なのかをご説明します。めまいは、自分や周りが動いていないのにもかかわらず、動いているように感じる状態です。
ぐるぐる回る感じだったり、ふわっとする感じだったり、景色が揺れる感じだったりします。
急に立ち上がったときに血の気の引く、立ち眩みの症状を、めまいと表現される方もいらっしゃいます。
いずれの症状にせよ、とても不快感を伴いますし、吐き気を感じたり、実際に吐いてしまうこともあります。動くことによって、めまいが悪化するため、病院に行くことさえ苦痛になってしまうこともあります。
めまいの症状が起こると、何科を受診すればよいのか、迷ってしまうこともあると思います。
そもそも、めまいは、いろいろな原因があるため、その原因によって診療科が変わってきます。ご自身で原因を判断するのは難しいですので、どの科を受診するか困ってしまうと思います。
そのような場合は、かかりつけ医に相談していただくか、耳鼻咽喉科や脳神経外科を受診するようにしましょう。適切な診断が行われ、場合によっては違う診療科に紹介してくれます。
めまいで一番多い原因は耳です
主なめまいの原因は、耳、脳、心臓です。それ以外に、姿勢や肩こりからくるめまいや、ストレスなどが原因の心因性めまいというものもあります。
耳の病気の場合は内耳性めまいと言い、耳はめまいの中で一番多い原因となります。
めまいがすると、脳に異常が起きたのではないかと心配される方が多いと思いますが、めまいを引き起こす原因となっているのは、耳のほうが圧倒的に多いのです。
めまいの中の60%程度が、内耳の問題と言われています。
この場合、耳鼻咽喉科の領域になりますので、耳鼻咽喉科での治療が必要になります。軽症の場合など、脳神経外科や内科での内服治療で対応可能なこともあります。
耳以外のめまいで、脳からくる中枢性めまいは脳神経外科や神経内科の領域になりますし、心臓など血液の循環の問題からくるめまいは、循環器内科が診療することになります。
耳のつくりと働きについて
耳は外側から、外耳、中耳、内耳と分類されています。その中で、めまいに関係するのは一番奥にある内耳です。内耳は、聴覚と平衡感覚を司る重要な器官です。内耳の機能障害は、めまいやバランスの問題をもたらします。
内耳の主要な部分は3つに分けられます。
蝸牛(かぎゅう)
音の振動を電気信号に変える、カタツムリのような形をした器官です。
蝸牛管の内部は、リンパ液で満たされていて、鼓膜からの振動は、このリンパを介して蝸牛神経を通じて脳に伝わります。
前庭(ぜんてい)
平衡感覚を司る器官で、体の傾きや加速度を感知し、平衡感覚を維持するのに役立ちます。
三半規管(さんはんきかん)
前庭とともに、平衡感覚を司る器官で、回転運動を感知し、体のバランスを保つために働きます。
***
これらの器官、とくに前庭や三半規管に不調が生じたときに、わたしたちはめまいとして症状を感じます。代表的なものに、メニエール病、良性発作性頭位めまい症、前庭神経炎が挙げられます。
良性発作性頭位めまい症は、英語表記のBenign Paroxysmal Positional Vertigoの頭文字をとってBPPVと呼ばれることが多いです。良性発作性頭位めまい症っていう名前は長いですからね。
めまいで最も多いBPPV
この中で最も多いのが、BPPVです。簡単に説明すると、内耳の耳石が異常に動くことで引き起こされるめまいで、特定の頭の位置をとるとめまいの発作が起こります。
BPPVは、めまいの中で最も多い、代表的な病気です。
たいていの場合は、じっとしている時には、めまいは起こらず、特定の頭の位置や、頭を動かすことで、めまいを感じます。天井や景色がぐるぐると回るように見えるので、回転性めまいと言われます。寝返りや、起床時、上や下を向いた時などにおこりやすいです。
めまいは数秒から数十秒でおさまりますが、頭を動かすたびに何度も繰り返し起こることが特徴です。メニエール病のように難聴や耳鳴といった聴覚のトラブルは伴いません。
BPPVの原因
三半規管の根元あたりに、重力や体の方向を感じ取る「耳石器」という器官があります。この中には、カルシウムでできた耳石と呼ばれる小さな石のようなものが入っています。これがはがれ落ちて、三半規管に入り込むことで、BPPVを発症します。
はがれた耳石は三半規管の中に浮かんでおり、頭を動かすと移動し、それがめまいを引き起こします。耳鼻咽喉科では、眼の動きを観察しながら、はがれた耳石のある場所を特定することができます。
BPPVの治療
通常、BPPVは数日から数週間で自然に治ってきます。しかし、ひんぱんにめまいを感じるのは辛いですので、耳鼻咽喉科で治療してもらうのが良いでしょう
多くの場合、頭の角度をゆっくり変えながら動かすことにより、はがれた耳石を元の位置に戻すことができます。そうすることによって、めまいの症状を改善させることができます。
この方法は浮遊耳石置換(ちかん)法にと呼ばれ、約70%以上の人が改善するといわれています。
対症療法として、薬を使うこともありますが、あまり効果は期待できません。薬の副作用のリスクも有るため、 頭位治療(浮遊耳石置換法)を第一に考えたほうが良いでしょう。
本人ができる浮遊耳石置換法も、ネットなどで紹介されていますが、耳鼻咽喉科にて診断を受けて、やり方の指導を受けてから行ってください。自己診断で治療を行うことは危険です。
診断そのものが間違っている可能性もありますし、症状の悪化にも繋がりかねません。
BPPVにおける誤解
頭を動かすと、ぐるぐる目がまわるので、患者さんの中には安静にして、頭を動かさないようにした方が良いと思っている方がいます。しかし、頭をめまいのする方向へ動かして、めまいを起こした方が、治りやすいことが知られています。
治すのに最も効果的な頭の動かし方もあります。耳鼻咽喉科で正しい診断と指導を受け、めまいの回復を促進させましょう。
聴力低下も伴うメニエール病
2番目に多い内耳性めまいとして、メニエール病があげられます。内耳性めまいの10~20%をしめると言われています。
メニエール病は、激しい回転性のめまいと聴力の低下、耳鳴り、耳の圧迫感を伴う耳閉感が主な症状です。そして、これらの症状が繰り返し起こるのが特徴です。
メニエール病の原因
内耳の内リンパ腔という場所はリンパという液体で満たされています。その液体が増えすぎて「内リンパ水腫」を起こすことが、メニエール病の本質と考えられています。
内リンパ液の過剰生成や吸収の障害により液体が増えてしまうのですが、その根本的な原因は明らかにはなっていません。
ストレスや遺伝的要因、アレルギー反応、ウイルス感染、血流障害などもメニエール病の発症に寄与する可能性があるとされていますが、これらの要因がどのように病気に影響を与えるかについては、さらなる研究が必要です。
メニエール病の症状
メニエール病の状態はいつも同じではなく、個人差があります。はじめは、耳の詰まるような閉塞感や、耳鳴り、低い音が聞こえにくいなど、聴覚の症状が目立つことがあります。
眼の前がぐるぐる回り、目を開けているのが辛く感じるような強いめまいを伴うこともあります。
重いめまいの発作が繰り返されたり、難聴や耳鳴りに悩まされたりします。人によっては耳の聞こえが悪くなって、元に戻らなくなってしまうこともあります。
メニエール病の診断が早く行われ、適切な治療が早く行われれば、1~2か月で症状がほとんど出現しなくなることもあります。めまいを何回も繰り返したり、症状を放っておくと、悪化したり、治療しても症状の改善が見られにくくなります。
メニエール病の治療
メニエール病の治療法は、症状の程度や患者さんの状態に合わせて、様々な方法が組み合わされます。なかなか改善せず、症状が繰り返し、難治性となる方もいます。
薬物治療としては、内リンパ液の量を減らし、内耳のむくみを改善させるために、利尿剤が用いられます。また、めまいや吐き気などの症状を緩和するために、抗めまい薬も使われます。
内耳の炎症を抑えるために、ステロイドが使われることもあります。また、ビタミン剤や漢方薬も処方されることがあります。
内服治療で治りにくい場合は、手術あるいは平衡機能訓練を行うことがあります。ひんぱんにめまいが起こって仕事ができないような時や、難聴の進行が早い時など薬で防げない時には、以下の手術が検討されることもあります。
手術には、内リンパ液を排出する内リンパ嚢ドレナージ術や、 めまいに関わる神経を切断する選択的内耳神経切断術などがあります。
高濃度の酸素を吸入することで、内耳の機能を改善する可能性があるため、高気圧酸素療法が行われることもあります。
生活習慣の改善も大切です
メニエール病の誘因として、さまざまなストレスや睡眠不足、過労などが関与していると考えられています。ストレスの貯めすぎや、睡眠不足には気を付けましょう。
生活習慣で関連性が指摘されているのは、塩分、水分、カフェインや喫煙、睡眠などです。
内リンパ液の量を調節するため、塩分摂取を控えるようにしましょう。むくみの原因となるので水分摂取量の調整も必要です。
カフェインは内耳の血管を収縮させる作用があるため、症状の悪化につながる可能性があります。喫煙も同様に内耳の血流を悪くし、症状を悪化させる可能性があります。
ストレスや疲労は、メニエール病の症状を悪化させる要因となりますので、ストレスをためないようにしましょう。適度な運動はストレス解消や血行促進に役立ちますので、無理のない範囲で取り入れましょう。
新しい治療法としての中耳加圧治療
2018年から、なかなか改善しない難治性のメニエール病に対して、新しい治療法として中耳加圧療法の保険適用が始まりました。薬が効かず、長年悩まされているメニエール病への有望な治療の選択肢と言えます。
中耳加圧治療は、耳鼻咽喉科にて、専用の中耳加圧装置を貸し出してもらい、自宅で朝晩2回、1回3分間加圧します。チューブの先から耳鼻科医が設定した空気の圧力で耳に刺激を与えて症状を改善するものです。
この中耳加圧療法は月一回の外来診療が必要ですが、在宅で治療ができ、約一年で80%の方に効果がみられています。
他の外科的な治療法より安価でリスクも低いため、注目されている新しい治療法です。気になる方は耳鼻咽喉科へご相談してみてください。
前庭神経炎
内耳性めまいの中で、よく見かける病気ではありませんが、前庭神経炎についても、知っておくと良いでしょう。
前庭神経炎は、内耳にある前庭神経が炎症を起こすことによって引き起こされるめまいです。前庭神経は、体のバランスを保つために重要な役割を果たしており、頭の位置や動きに関する情報を脳に伝えています。
前庭神経炎の症状
前庭神経炎の主な症状には、突然起こる強い回転性のめまいが挙げられます。そのほかに、平衡感覚が低下したり、吐き気、嘔吐などを伴うことがあります。
これらの症状は、数日から数週間続くことがありますが、徐々に改善することが多いです。
前庭神経炎の原因
前庭神経炎の原因は、ウイルス感染(特に風邪やインフルエンザウイルス)によるものが一般的とされていますが、まだ完全には解明されていません。自己免疫疾患などの関与も考えられています。
前庭神経炎の治療法
前庭神経炎の治療法は、まずはめまいや吐き気の症状を抑えることです。そして原因に応じて、再発予防が目的となります。
薬物療法としては、めまい止めや吐き気止めの薬を使います。前庭神経の炎症を抑えるためにステロイドも用います。めまい、吐き気で水分が取れず、脱水症状になっている方には、点滴治療も行います。
平衡感覚の回復を促すために、リハビリテーションを行うこともあります。
予防
前庭神経炎の予防法は、まだ確立されていませんが、ストレスを溜めないことが大切です。十分な睡眠をとり、バランスの取れた食事を心がけるなど、健康的な生活習慣を送るようにしましょう。
内耳性めまいのまとめ
内耳性めまいの症状は、回転性のめまいや不安定感、吐き気、嘔吐などが含まれます。診断には、医師による問診、身体検査、聴力検査、平衡機能検査などが行われます。
治療方法は原因によって異なりますが、薬物療法、リハビリテーション、場合によっては手術が考慮されることもあります。特にBPPVの場合は、特定の体位を用いた頭位治療法が効果的です。メニエール病では、治療が遅れると治りが悪くなることもあります。
内耳性めまいは生活の質に大きな影響を与えることがあるため、早期の診断と適切な治療が重要です。
脳からくるめまい(中枢性めまい)
先程からめまいの原因は耳からのことが多いと書きましたが、めまいの他に、意識障害、ことばの障害、運動麻痺、知覚麻痺、激しい頭痛などを伴う場合は脳卒中の可能性が出てきます。
緊急な対応が必要ですので、救急車を呼ぶなどの対応をしてください。脳神経外科や脳神経内科にて対応することになります。
小脳が障害を受けるとめまいが生じます
めまいを引き起こしやすい脳卒中の場所は、小脳や脳幹です。特に、小脳は体のバランスを保つ上で重要な働きをしており、この部位の出血や梗塞により、めまいや嘔吐が生じます。
脳幹の場合は、麻痺や話しにくさを伴うことが多いです。
小脳は出血も梗塞も起こすことがありますが、いずれも小脳の機能異常が生じ、バランス感覚が障害されます。出血のほうが強い頭痛を伴うことが多いですが、症状から脳梗塞か脳出血かは判断できないこともあります。
いずれも、一刻も早く治療を行う必要があります。
小脳の脳卒中の原因
脳梗塞、脳出血など脳の血管の障害で起こる病気を脳卒中と呼びます。
小脳の脳卒中の原因も、一般的な脳卒中の原因とほとんど変わりありません。
高血圧は血管のダメージを引き起こします。高血圧が続くと、血管がもろくなり、破れやすくなります。
また、血管の内部にプラークというコレステロールやカルシウムなどの塊がたまりやすくなってしまいます。それにより、血管の内径が狭くなり、血流が悪くなります。
小脳を栄養する血管が破れると小脳出血となり、血管が詰まってしまうと小脳梗塞になります。
その他、脳動脈瘤や血管奇形、血液疾患などが原因となり、小脳出血や小脳梗塞になることもあります。
小脳の脳卒中の場合は、めまい以外の症状も伴いやすいです
小脳の脳卒中の症状は、障害される場所や大きさによって異なりますが、主な症状としては、めまい、吐き気、嘔吐。頭痛、ふらつき、話しにくさなどがあります。
内耳性めまいも、吐き気や嘔吐を伴いますが、ろれつが回らなかったり、手の動きがぎこちない、意識障害などの症状を伴うときは、小脳や脳幹の異常を疑います。
脳卒中によるめまいの治療
出血と梗塞では治療法が異なりますが、少しでも早く診断し、治療にあたることが重要です。
発症してしまうと、命にかかわる場合や、重い後遺症を残してしまう可能性があります。
小脳出血
小脳出血の治療は、出血の大きさや状態によって異なります。
薬物療法としては、血圧を下げる薬や、脳の腫れを抑える薬などが用いられます。出血が大きい場合には、手術で血腫を取り除くことがあります。
小脳梗塞
発症後4.5時間以内の場合は、血栓を溶かす薬を投与し、血流を再開させる治療法(血栓溶解療法:t-PA療法)を行うことがあります。
そのほか、血液をサラサラにする薬や、血栓の形成を予防する薬などを使用します。
脳細胞を保護する薬や、脳の腫れをとる薬も使用することがあります。脳の腫れが強い場合は、手術を行うこともあります。
小脳出血、小脳梗塞とも長期のリハビリテーションが必要になることがあります。
小脳の脳卒中を予防するには
出血、梗塞、いずれも血管を健康に保つことが予防につながります。
高血圧の方は、血圧を適切に管理することが重要です。塩分を控えたバランスのとれた食事をとり、適度な運動を行いましょう。
喫煙は動脈硬化の原因となりますので、禁煙しましょう。紙たばこだけでなく、電子タバコも控えるようにしましょう。ご自身で、禁煙が難しい場合は、禁煙外来を受診するのも良いでしょう。
糖尿病、脂質異常症は、動脈硬化を進行させる原因となりますので、定期的に検査を行い、必要に応じて治療を行いましょう。
原因不明の慢性的なめまい症
慢性的なめまいの症状が続く場合、持続性姿勢知覚めまい:PPPD(Persistent Postural-Perceptual Dizziness)かもしれません。
PPPDは、慢性のめまいの原因として最も多いのではないかといわれています。
これまで、原因不明のめまい症と言われてきたものの多くを占めます。長期間にわたって、めまいの症状が持続するのが特徴です。数ヶ月以上続くことがあります。
めまいの症状は、特定の姿勢や動作に関連して悪化することが多く、特に立っているときや動いているときに感じやすいです。
まわりの動きや自分自身の動きに対する過敏性が増し、周囲のものが揺れているように感じたり、ふわふわした感覚を伴うことがあります。
ストレスや不安、過去のめまいエピソードが引き金となることが多く、心理的な要因が症状に影響を与えることがあります。
PPPDは、他のめまいの原因によって引き起こされることが多いのです。しかし、これらの原因が解消された後も症状が持続してしまいます。
治療には、認知行動療法や理学療法が有効とされていますが、まだ分かっていないことも多いです。ストレスや疲労によって症状が悪化することがありますので、気をつけていきましょう。
まとめ
今回はめまいについて説明させていただきました。
めまいで最も多いのは、耳が原因であるBPPV(良性発作性頭位めまい症)です。適切な診断と治療で治りやすい病気です。
そのほかには、メニエール病や、脳卒中がありますが、早期診断、早期治療が重要です。
めまいを感じた場合は、放置したり、自己診断をするのではなく、病院を受診しましょう。
参考
一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
一般社団法人日本めまい平衡医学会