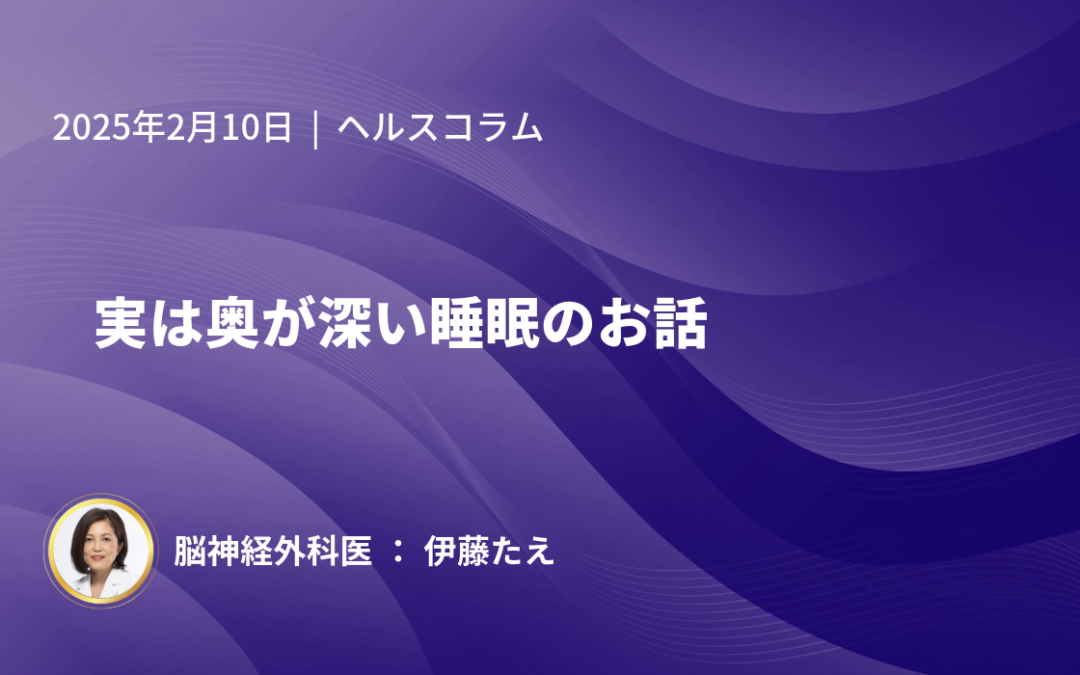この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)
【経歴】
2004年3月 浜松医科大学医学部卒業
2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修
2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局
2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務
2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務
2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務
2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科
菅原クリニック東京脳ドック 院長
【専門】
日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医
【資格・免許】
医師免許
今日は睡眠についてお話ししたいと思います
私たちは人生のうち3分の1の時間を睡眠に費やしています。
若い頃は、やりたい事や、やらなければならない事がいっぱいで、寝る時間がもったいないと思って、夜遅くまで起きたりしていました。しかし、最近は睡眠の重要さに気づかされることが多いです。睡眠不足が続くと、頭の働きが鈍くなりますし、体がもちません。
睡眠は食べることと同様、生命活動にとって必要不可欠なもので、良質な睡眠があってこそ、健康な生活になるのです。
睡眠はノンレム睡眠とレム睡眠の2つのフェーズを繰り返します
まずは、ご存じの方も多いと思いますが、睡眠の種類について簡単に説明しようと思います。睡眠は大きくはノンレム睡眠とレム睡眠の2つのフェーズに分けられます。
ノンレム睡眠は、身体が休息状態にあることを反映して、筋肉の動きだけでなく、心拍や呼吸、体温なども低下し安定します。また、脳の活動も低下し、休息している状態です。
それに対し、レム睡眠の「レム」は、英語の急速眼球運動(Rapid Eye Movement)の略語で、字の通り、睡眠中に眼球が素早く動きます。ノンレム睡眠とは逆に、血圧、呼吸や心拍も大きく変動します。
睡眠はノンレム睡眠から始まり、その後にレム睡眠が続きます。私たち人間のノンレム睡眠とレム睡眠のサイクルは約90分で、一晩の睡眠中にこのサイクルを4〜5回繰り返します。
睡眠には休息以外の重要な役割もあります
最初の深いノンレム睡眠が起こるときに、成長ホルモンの分泌が増えます。成長ホルモンは骨や筋肉の発達にかかわるホルモンです。「寝る子は育つ」ということわざも納得ですね。
大人にも成長ホルモンは大切で、代謝を促進する働きがあります。
代謝の促進によって、傷の治りを促したり、肌のつやを維持する効果もあります。アンチエイジングのクリニックで、成長ホルモンが使われるのは、この働きがあるからです。
それ以外にノンレム睡眠中に起こることとして、最近注目されているのは、老廃物の除去作用です。
起きているときに脳に溜まった老廃物が脳の外に排出されるのです。その中には アルツハイマー病の脳に多く見られるアミロイドβタンパク質も含まれるので、十分な睡眠が、とても重要なことがわかります。
睡眠には、日中に学習したことの記憶を定着させる働きもあります。
ですので、睡眠を削って暗記をしても、一時的に覚えているだけで、すぐに忘れてしまいます。テスト勉強で、一夜漬けの経験がある方も多いでしょう。どうにかテストで解答できても、数週間後にはすっかり記憶が抜け落ちてしまっていた、なんていう思い出がある方もいるのではないでしょうか。
このような重要な働きを持つ睡眠ですが、日本人はあまり十分にとれていないと言われています。
令和元年の国民健康・栄養調査結果によると、1日の平均睡眠時間が6時間未満の人の割合は、男性 37.5%、女性 40.6%と、とても多くの人が十分な睡眠時間をとれていないことが分かりました。とくに、男性の 30〜 50 歳代、女性の 40〜50 歳代では、4割以上の方が睡眠を十分にとれておらず、十分な睡眠の確保は重要な健康課題となっています。
睡眠不足は心身ともに悪影響を引き起こします
睡眠不足は、日中の眠気や疲労だけではなく、頭痛や気分の不安定さ、注意力や判断力の低下につながることが分かっています。仕事の効率も落ちますし、子供では学業成績の低下にもつながります。
慢性的な睡眠不足は、肥満、高血圧、糖尿病につながります。心疾患、脳血管障害になる危険性をあげることも分かっています。さらには死亡率の上昇にも関与することが明らかとなっています。
メンタル面でも睡眠不足は悪影響を及ぼします。うつ病や認知症などの発症リスクをあげるという研究結果が、最近報告されています。7時間前後の睡眠時間の人が、生活習慣病やうつ病の発症や、死亡に至るリスクが最も低いのです。
しかし睡眠時間が長ければいいというものではなく、7時間より長い睡眠も短い睡眠もこれらのリスクを増加させることが報告されていますので、適度な睡眠時間が重要となります。
「寝だめ」は睡眠を貯められません
なかなか毎日、十分な睡眠時間を確保できない人も多いと思います。
平日は仕事が遅くまで長引いてしまい、寝る時間が遅くなってしまい、睡眠不足になっている人もいるでしょう。平日は十分な睡眠がとれないけれど、週末まとめて睡眠をとっているから大丈夫と思っている人はいないでしょうか。
平日の睡眠不足(睡眠負債)を、休日に取り戻そうと長い睡眠時間を確保する「寝だめ」の習慣がある人は少なくありません。
しかし、この「寝だめ」は、世界では「社会的時差 ボケ」(Social Jetlag)とも呼ばれています。「寝だめ」だと睡眠を貯めておくという良いイメージを持ちがちですが、「時差ボケ」と聞くと体に悪そうですよね。
実際に、睡眠をためることはできませんし、何度も体内時計がずれてしまうことによって、逆に健康へ悪影響を及ぼすこともあります。
平日はあまり眠れないからといって、あらかじめ休日に睡眠時間を長時間確保することはやめましょう。疲れ切って、週末たくさん寝てしまう場合は、平日の睡眠の見直しが必要です。
休眠休養感は睡眠時間と同様にとても重要です
良質な睡眠について考えるにあたっては、睡眠時間以外にも重要なポイントがあります。それは睡眠休養感といって、朝目覚めた時に感じる休まった感覚のことです。
睡眠時間は取れているのに、何故か体がスッキリしないとか、日中眠くなってしまう場合は、この睡眠休養感が足りていない可能性があります。
睡眠休養感は、生活習慣病やメンタルに影響するため、健康な生活を送るには、十分な睡眠時間の確保はもちろんのこと、それと同じくらい睡眠により休養感が得られることが重要です。
睡眠休養感を低下させる原因は多岐にわたります。仕事や学業、対人関係などによる日中のストレスは、やはり大きく影響します。就寝直前の夕食や夜食、朝食抜きなどの食習慣の乱れや、運動不足も睡眠休養感の低下に繋がります。
そして糖尿病、高血圧、がん、うつ病などの病気があっても、睡眠休養感は低下することが報告されています。睡眠休養感を向上させるためには、生活習慣の見直しが重要になりますし、日中のストレスを持ち越さないために、寝る前のリラクゼーションも大切です。
ライフステージごとに必要な睡眠時間は異なります
では次に、どのような睡眠を取ればいいのか説明していきます。必要とされる睡眠は、ライフステージごとに異なってきます。おおまかに、こども、成人、高齢者にわけて、睡眠に関する推奨事項を示していきます。
子どもの睡眠時間
こどもの睡眠時間は、さらに年齢別に細かく分けられています。それぞれ定められた推奨睡眠時間は次の通りです。1〜2歳児は11〜14時間、3〜5歳児は10〜13時間、小学生:は9〜12時間、中学生・高校生:は8〜10時間です。
最近は子供の睡眠不足も問題になっています。受験勉強で、子どもの睡眠時間が削られるようなことは避けなくてはならないです。
先ほどお話ししたように、睡眠は記憶の定着にも影響しますので、睡眠を削っての勉強は、学習面でも逆効果になりかねません。もちろんスマホなどの電子機器で夜ふかしをするのは、もってのほかです。
成人の睡眠時間
成人後は、20年ごとに30分程度の割合で夜間の睡眠時間が減少していくと言われていますが、6時間以上の睡眠が推奨されています。
しかし、睡眠時はかなり個人差があり、みなさんもお聞きになったこともあるかと思いますが、ロングスリーパーやショートスリーパーの方もいらっしゃいます。ロングスリーパーは9時間以上の睡眠が必要なひとで、ショートスリーパーは6時間以下の睡眠で足りるひとです。これらの特徴は、遺伝的な要因や、精神的な要因、生活環境によります。
ロングスリーパーが、平均的な睡眠時間しか睡眠をとらなければ、睡眠不足を招きます。逆に、ショートスリーパーが平均的な睡眠時間にこだわりすぎるのもよくありません。
平均時間を寝ようとすると、なかなか寝付けずに、眠れないことが逆にストレスになりかねません。
少ない睡眠時間で日中も元気に過ごせるなら、楽しめる時間が増えるので、ショートスリーパーをうらやましく思う方もいるかもしれません。しかしながら、ショートスリーパーは、人口の数パーセント程度と非常に少なく、体質的なもので、努力してもなれません。無理してショートスリーパーになろうとすると、体を壊しかねませんので、やめておきましょう。
高齢者の睡眠時間
ご高齢の方は、寝ている時間が長くなりすぎると、逆に健康リスクになるので注意が必要です。
個人の体調や生活状況に合わせて睡眠時間を考えなければなりませんが、寝ている時間が8時間以上にならない方が良いと言われています。長時間の昼寝も体に悪影響を及ぼすので、注意が必要です。
認知症の発症リスク調査で、睡眠時間5〜7時間のケースが最も認知症になりにくかったという結果もあります。高齢になれば必要とされる睡眠時間が減りますので、無理に長時間の睡眠を確保しようとしなくていいと言えます。
たまにクリニックに、早く目が覚めてしまい、十分眠れないので睡眠薬がほしいと受診される高齢の方がいらっしゃいます。睡眠について問診を行うと、夜は10時に寝て、朝4時半に目が冷めて、再度眠れないのでご自身は睡眠不足だと思うとのこと。
この場合6時間半寝ていますので、日中に眠くならないようでしたら、問題ありません。早朝の時間を有意義に使いましょう。逆に、日中に眠くなり、昼寝をしているようなら、まずは昼寝の時間を減らすことが大切です。
良質な睡眠をとるために心がけたいこと
では、ここからは、良質な睡眠を得るための方法を紹介していきます。
太陽の光と夜間の明るさ
まずは、太陽の光を浴びることです。日中にできるだけ日光を浴びると、体内時計が調節されて、寝付きが良くなります。
これは、日中に光を多く浴びることで、夜間のメラトニン分泌量が増加することによります。メラトニンは、体内時計に働きかけ、眠気を誘い、質の高い睡眠へと導いてくれます。
周囲が暗くなるにつれてメラトニンの分泌が活発になりますが、そのときに光を感知すると、メラトニンの分泌は抑制されます。このため、夜に照明やスマートフォ ンの強い光を浴びると、メラトニンの分泌が抑えられてしまい、入眠が妨げられます。
照明器具やスマートフォンにはLEDが使用されており、ブルーライトが含まれます。ブルーライトは体内時計への影響が強い短波長の光です。
寝室にはスマートフォンやタブレット端末を持ち込まないようにしましょう。照明は、全部消せれば一番いいですが、夜中トイレに行くときなどのことも考えると、LEDを使用していない足元だけの間接照明などを設置することも良いと思われます。
寝る前に体を温める
寝る前に体を温めることも効果的です。体が温まると、手足の血流が増え、体温が外に放出されます。それによって深部体温が低下し始めることで、入眠しやすい状態になるのです。
寝る時間の1〜2時間程度前に入浴するのが効果的と言われています。朝にシャワーを浴びて、目を覚まさせる習慣の人は、夜の入浴を試してみるのもよいでしょう。寝つきが良くなり、朝にシャワーを浴びなくても、しっかり目が覚めるようになるかもしれません。
自分の体を温めるだけでなく、睡眠時の温度環境も重要です。寝室は暑すぎず寒すぎない温度にしましょう。エアコンや加湿器を上手に利用しましょう。
また、できるだけ静かな環境で寝ることも、良質な睡眠につながります。リラックスできる寝衣・寝具で眠ることも睡眠の質を向上させます。
日々の運動習慣は大切
日中の生活で取り入れてほしいのは、適度な運動習慣です。
運動習慣は、良質な睡眠の確保に役⽴ちます。ウォーキングやジョギングのような有酸素運動は、寝つきを良くし、睡眠休養感も高めると報告されています。筋力トレーニングも、睡眠改善に効果があるといわれていますので、取り入れてみるのが良いでしょう。
運動習慣がない人は、 睡眠休養感が低いこと がわかっています。そのため、適度な運動習慣により、日中に身体をしっかり動かすことは、入眠の促進や 中途覚醒の減少を通じて、睡眠時間を増やし、睡眠の質を高めます。
朝食をとり夜食を控える
しっかり朝食を摂り、就寝直前の夜食を控えることも大切です。食生活が体内時計の調整に影響するためです。
1週間程度、朝食を抜いてしまうと、体内時計が後退することが報告されています。それにより、寝つきが悪化し、睡眠不足を生じやすくなります。
就寝前の夜食や間食も同様に体内時計を後退させてしまいますので、避けなければいけません。そのうえ、就寝前の摂取カロリーオーバーは、糖尿病や肥満の原因になり、閉塞性睡眠時無呼吸の発症リスクも高めることが報告されています。
塩分の取りすぎも睡眠に影響します。日中に摂取した食塩の過剰分は、睡眠中に排泄されるため、 夜のトイレ回数が増えてしまうからです。減塩食は良質な睡眠にもつながるので、日ごろから心がけることが大切です。
それ以外の睡眠に良い食事としては、地中海食があげられますが、睡眠の質を直接改善する個別の食品等は特定されていません。
地中海食は、魚、野菜、果物、ナッツ・豆類を中心とした食事内容となります。様々な食材を取り入れてバランスよく食べることをお勧めします。
カフェインの摂取に注意
日中の眠気覚ましにコーヒーを飲む方も多いと思います。コーヒーに含まれるカフェインが眠気を飛ばしてくれるのですが、摂取量や時間に注意が必要です。
カフェインの摂取量が、1日400mg(コーヒーを700cc程度)を超えると、夜眠りにくくなる可能性 があります。
また、カフェインの夕方以降の摂取は、夜間の睡眠に影響しやすいです。カフェインの摂取総量を減らすとともに、夕方以降はカフェインが含まれる飲み物や食べ物をとることを控えるようにしましょう。
コーヒー以外に紅茶や煎茶、ウーロン茶などお茶類にはカフェインが含まれているものが多いです。
麦茶、そば茶、黒豆茶、コーン茶などはカフェインが含まれていないので、夜に飲んでも問題ありません。その他にも、カフェインを含まないハーブティーなどに置き換えるのも良いでしょう。
お酒で寝るのはやめましょう
お酒を飲むと眠りやすいから、寝る前にお酒を飲むという話はよく聞きます。
たしかに、アルコールは一時的には寝つきを良くして、睡眠の前半では深い睡眠を増加させます。しかし、睡眠の後半では、眠りの質が顕著に悪化します。飲酒量が増加するにつれて、中途覚醒回数が増加することも報告されています。
それ以外にもアルコールは、閉塞性睡眠時無呼吸をはじめとしたさまざまな睡眠障害を増悪させますので、注意が必要です。くれぐれも、寝るためにお酒を飲むということはやめておきましょう。
喫煙も睡眠に影響します
喫煙も睡眠に悪影響を及ぼします。紙たばこ以外に加熱式たばこ、電子たばこも当てはまります。たばこに含まれるニコチンが覚醒作用を持っているからです。
睡眠前の喫煙は、寝つきを悪化させたり、中途で起きてしまう回数を増やします。深い睡眠の量も減るといわれています。
ニコチンの血中半減期(血液の中の濃度が半分になる時間)は約2時間なので、夕方の喫煙が、眠る前までニコチンの作用を残してしまう可能性があります。
習慣的にニコチンを摂取している人は、非喫煙者と比べて、入眠困難・中途覚醒が多く、睡眠時間、深い睡眠が減少し、日中の眠気も強いことが報告 されています。
規則正しい生活が大切です
そして一番大切ともいえるのは、やはり、規則正しい生活を送るということです。
規則正しい生活習慣で、日中の活動と夜間の睡眠のメリハリをつけることが、睡眠の質を高めるのです。睡眠の質が高まれば、日中に眠気やだるさを感じることも減ってきます。
一方で、夜ふかし、不規則な就寝時刻、不規則な食事時間や偏った食事などの生活習慣の乱れは、睡眠不足を招くだけでなく、体内時計の遅れや乱れや、主観的な睡眠の質の低下を招きます。
睡眠休養感が少ないのは病気が潜んでいる可能性も
睡眠時無呼吸症候群
閉塞性睡眠時無呼吸症候群のような睡眠障害が潜んでいると、睡眠環境、生活習慣、嗜好品のとり方などを改善しても睡眠休養感が十分に得られません。
睡眠時無呼吸症候群は、寝ている間に何度も呼吸が止まってしまうため、眠りが浅くなり、質の良い睡眠が取れなくなってしまう病気です。
大きないびきをかいたり、睡眠中に呼吸が止まるようなら、耳鼻科や呼吸器内科など睡眠時無呼吸外来を行っている病院で検査をする必要があります。
一人暮らしの場合気づきにくいこともありますが、自分のいびきの大きな音で起きてしまったり、呼吸が止まり苦しくなって、起きてしまうことで無呼吸に気づくこともあります。
睡眠時間は確保しているのに、日中に眠気やだるさを感じたりする場合も、疑う必要があります。
レストレスレッグス症候群
レストレスレッグス症候群(従来はむずむず脚症候群と呼ばれていました)も睡眠障害につながります。
これは、夕方から深夜にかけて、足を中心に異常な感覚が出現してくる病気です。
足を動かすと、この異常感覚が消え、じっとしていると再び出現するため、布団の中でじっとしていられません。そのため、寝付きにくいし、睡眠が浅く、十分に眠れなくなってしまいます。
また、足が周期的にピクッピクッと勝手に動き続けていることが多く(周期性四肢運動障害)、これも睡眠を浅くする原因となります。
精神疾患
うつ病などの精神疾患も睡眠障害に関係しています。
うつ病では高い確率で不眠症状が伴います。その逆に過眠状態になることもあり、不眠と仮眠を繰り返すこともあります。
睡眠が短くなったり長くなったりすると、睡眠休養感が慢性的に得られにくくなってしまいます。認知症の方も睡眠障害が出やすいので、適切な対応が必要です。
まとめ
今回は睡眠について、お話しさせていただきました。
適切な睡眠習慣をつけ、十分な睡眠休養感を得られるようにしましょう。
参考文献
日本睡眠学会
https://www.jssr.jp/basicofsleep
健康づくりのための睡眠ガイド2023
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
Good Sleepガイド
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001222161.pdf