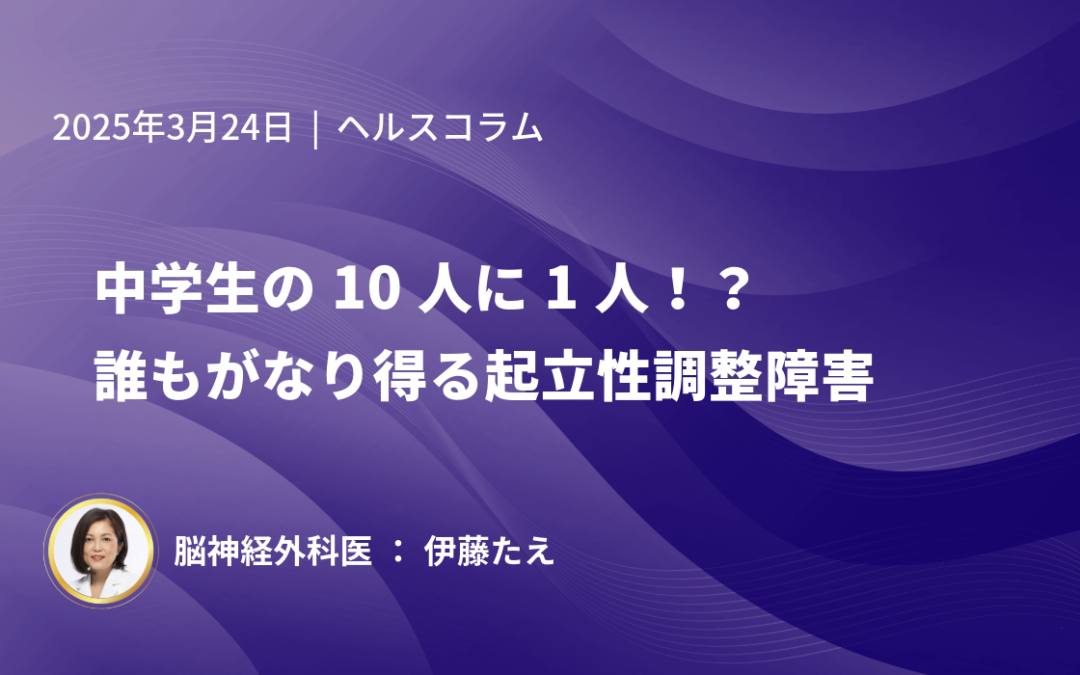この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)
【経歴】
2004年3月 浜松医科大学医学部卒業
2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修
2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局
2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務
2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務
2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務
2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科
菅原クリニック東京脳ドック 院長
【専門】
日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医
【資格・免許】
医師免許
起立性調節障害という病気をご存知でしょうか?
小学生から大人まで、誰もがなる可能性のある病気です。中学生の1割が、この起立性調節障害に悩まされているという報告もあります。
見た目ではわかりにくいですし、朝起きられない、学校に行けないなど、ただサボっているのではないかなどと、周囲から誤解を受けがちです。
思春期のお子様がなりやすいので、親御さんからの理解が得られないと、なかなか精神的にもつらい状況になってしまいます。
今回はこの起立性調節障害という病気についてご説明していきます。
起立性調整障害の症状
起立性調節障害の症状は、特に子供では日内変動が大きいです。
午前中は交感神経が活性化しないため、なかなか起きられません。立ち上がった時にふらついたり、めまいを感じたりします。
朝の調子が悪いと、学校にいけなくなってしまい、勉強についていけなくなることもあります。
時間とともに交感神経が活性化してくるため、夜は元気になっていることも多いです。そして、遅い時間になっても、交感神経の興奮状態が続き、寝付けなくなってしまいます。
朝起きれなくて、夜眠れないという悪循環に陥ってしまいます。
この悪循環は、睡眠相後退症候群と呼ばれています。放置すると昼夜逆転生活になってしまう危険があります。
起立性調節障害の頻度
起立性調節障害は、小学生高学年から中学生にかけて多く認められます。
ちょうど思春期の時期で、体や心が子供から大人に変化する時期です。この変化は自律神経にも影響し、交感神経と副交感神経のバランスが乱れやすくなるのです。
小学生で約5%、中学生では約10%の子供が、起立性調節障害の症状を経験すると言われています。
発症して1年後には半数が回復すると言われていますが、重症化すると大人になっても症状が残ってしまうこともあります。
起立性調節障害はどうして起こるのか
自律神経は、交感神経と副交感神経に分けられ、それぞれが異なる働きをします。
この交感神経と副交感神経が、バランスよく作用することによって、私達は健康的な生活を送ることができます。起立性調節障害は、このバランスが乱れることにより引き起こされます。
交感神経は体を活動させるための神経で、副交感神経は体を休ませるための神経です。
バランスが乱れる原因としては、ストレスや生活習慣の乱れも挙げられますが、体質や遺伝的な要素も影響します。
起立性調節障害の約半数に、遺伝の可能性が指摘されています。もともと朝が弱かったり、立ち眩みを起こしやすい体質など、自律神経の働きには個人差があります。
水分と塩分は血圧に大きく関与しているため、脱水や塩分不足で立ち眩みが起こりやすくなります。しかし、塩分も水分も取りすぎは病気に繋がりますし、心臓や腎臓の病気の方は特に注意が必要です。
筋力低下も起立性調節障害の原因になります。特に下肢の筋肉は、立った時に下肢に滞った血液を心臓に戻すポンプ作用があるためです。
ストレスも自律神経の乱れを引き起こします。真面目な人や精神的ストレスを受けやすい方は要注意です。
不規則な食生活や偏食も自律神経の乱れの原因になりますし、睡眠の乱れも自律神経に悪影響を及ぼします。
起立性調節障害の症状
交感神経の乱れが生じ、起立性調節障害になってしまうと、以下のような症状が現れます。
- 寝つきが悪く、朝起きるのが辛くなる。
- 倦怠感がつづき、微熱が続くこともある。
- 立ち眩みが起こりやすく、立っていると気分が悪くなる。
- 集中力が続かず、イライラしやすくなったり、学校の成績も下降しがち。
- 顔色が良くなく、ストレスを感じるとすぐに気分が悪くなる。
起立性調節障害の初期症状は、はっきりと病気と感じるようなものではなく、ささいなものです。単なる甘えやさぼりと思われてしまうかもしれません。
誰もがなりえる病気です。小学生高学年から中学生にかけてのお子さんがいらっしゃる家庭では、お子さんの不調の時は、起立性調節障害も疑う必要があります。
受験勉強や親からの過度の期待や干渉がストレスとなっている場合もありますので、注意が必要です。
イライラが強く親にあたったりする場合、単に反抗期と決めつけるだけでなく、起立性調節障害の可能性も考えましょう。
起立性調節障害の診断
まずは、困っている症状や、生活リズムなどについて丁寧な問診を行います。
診察、基本的な血液検査、内分泌学的検査、心電図などを必要に応じて実施します。採血などで異常が見つかれば、別の病気がないか、さらに精密検査を行うことになります。
起立性調節障害の検査としては、体位の変換にともなう血圧や脈拍の変化を調べます。新起立試験という検査です。
10分間ベッドに寝てじっとし、その後1分毎に10分間、血圧・心拍数を測定します。血圧・心拍数の回復具合をみて、診断を行います。
検査は朝と午後では全く違う結果が得られてしまうので、朝の不調時に行います。
起立性調節障害の治し方
睡眠リズムを整える
規則正しい睡眠リズムは健康の土台です。
起立性調節障害はこの睡眠リズムが乱れてしまっています。
光環境を整える
朝は太陽の光を浴び、体内時計を調整しましょう。
夜は光を浴びる時間を少なくし、特にスマートフォンやパソコンのブルーライトには気をつけましょう。
腸内環境を整える
頭痛、めまい、倦怠感などと腸内環境が関連している可能性が指摘されています。
脳腸相関という言葉があり、これは、生物にとって重要な器官である脳と腸が、お互いに密接に影響を及ぼしあうことを示す言葉です。
栄養の補給
成長期には十分な影響が必要です。
バランスの良い食事を、規則正しく摂りましょう。無理なダイエットはしてはいけません。
薬物療法
血圧を上げる薬を用いることがあります。
起き上がると血圧が下がって、調子が悪くなるので、それに対する対処療法です。しかし、上述の生活環境の改善や、周囲の理解が重要となります。
参考
起立性調節障害改善協会
https://odod.or.jp/