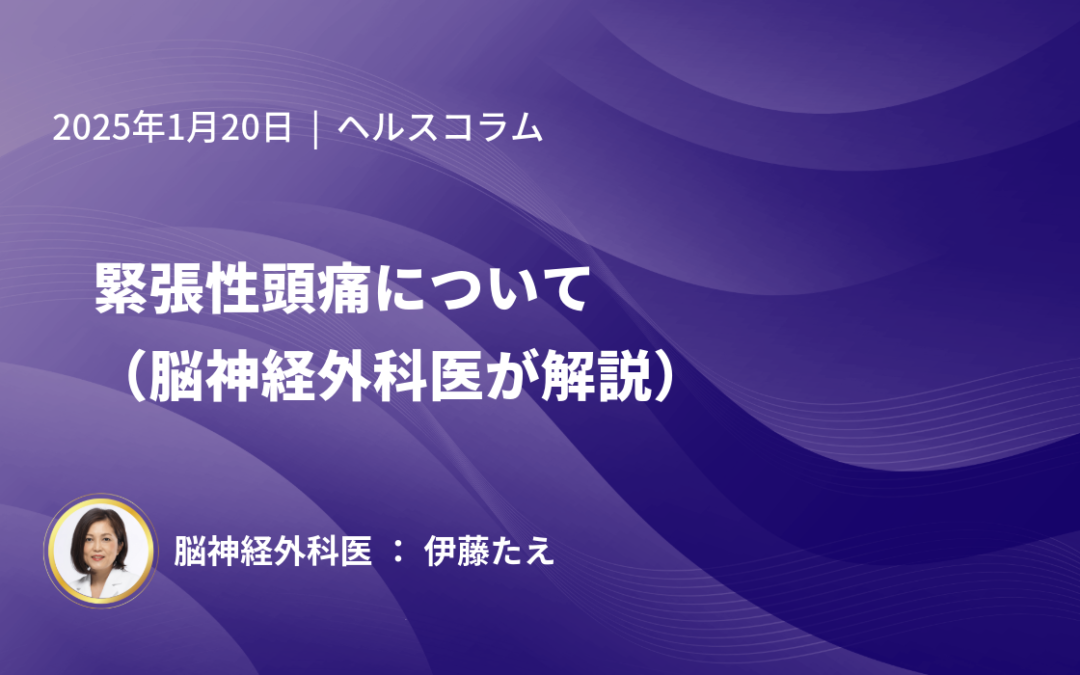この記事の著者

【氏名】伊藤たえ(脳神経外科医)
【経歴】
2004年3月 浜松医科大学医学部卒業
2004年4月 浜松医科大学付属病院初期研修
2006年4月 浜松医科大学脳神経外科入局
2013年7月 河北総合病院 脳神経外科 勤務
2016年9月 山田記念病院 脳神経外科 勤務
2019年4月 菅原脳神経外科クリニック 勤務
2019年10月 医療法人社団赤坂パークビル脳神経外科
菅原クリニック東京脳ドック 院長
【専門】
日本脳神経外科専門医 日本脳卒中学会専門医
【資格・免許】
医師免許
頭痛にはどのような種類があるのか
一言で頭痛と言っても、いろいろな種類の頭痛があります。国際頭痛分類委員会という国際的な機関によって、頭痛は細かく分類されており、大きくは一次性頭痛と二次性頭痛に分けられます。
緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛が代表的な一次性頭痛に当てはまります。頭痛の原因になる別の病気が認められないのが一次性頭痛です。
逆に、別の病気が原因で頭痛を引き起こしている状態が二次性頭痛です。脳腫瘍や髄膜炎、副鼻腔炎など様々な病気が含まれます。
緊張型頭痛の特徴は
緊張型頭痛は、頭全体が締め付けられるような痛みが特徴です。ハチマキで頭を強く締め付けられたような感じと表現されることもあります。片頭痛がズキンズキンと形容されるのに対して、こちらはギューというような持続的な痛みです。
軽い痛みが慢性的に続くことが多く、日常生活に支障をきたすことは少ないです。しかし、とても痛くて、吐き気を伴うような場合もあります。また、頭痛時にふわふわしためまいを伴うこともあります。
動くと悪化する片頭痛とは逆に、体を動かして、血行を良くすると改善する傾向にあります。デスクワークの姿勢は、緊張型頭痛を悪化させがちで、一日中仕事した後の夕方頃に、悪化しやすいです。
緊張型頭痛になっている方は、たいてい肩こりや首こりを感じています。パソコン作業やスマホ操作が多かったり、長時間、同じ体勢で作業をしなければならない人は注意が必要です。
緊張型頭痛になる人の頻度は
緊張型頭痛は頭痛の中で最も多い頭痛です。世界中で悩まされている人がたくさんいます。3人に1人が、一生のうちに緊張型頭痛を経験することがあるといわれています。
子どもは緊張型頭痛になりにくいですが、スマホやパソコンの使用の低年齢化や、使用時間の増加により、最近は増加傾向です。
片頭痛ほどではないですが、緊張型頭痛も女性に多い傾向があり、男性の2倍程度といわれています。緊張型頭痛と関連が強い肩こりも、女性のほうが男性の2倍程度多く悩まされています。このことから、筋肉量が少ないことや、体が冷えやすいことが影響していると考えられています。
緊張型頭痛の原因について
首や肩の筋肉が緊張することで、緊張型頭痛は引き起こされます。筋肉が緊張する原因としては、長時間にわたって同じ姿勢で作業することや、猫背などの筋肉に負担がかかる姿勢が挙げられます。デスクワークやスマホの使用が大きく影響しています。
精神的なストレスや不安も、筋肉の緊張の原因になります。仕事や人間関係がうまくいかないときに、緊張型頭痛は起こりやすくなります。睡眠不足や不規則な生活、運動不足も原因となります。最近では、リモートワークによる運動不足も問題になっています。
体の冷えも血行を悪くして、筋肉を緊張させ、緊張型頭痛を引き起こします。寒い冬だけでなく、夏場の冷房も原因となりますので、気をつけましょう。
睡眠時の枕が、自分の体にあっていないと、本来、緊張を緩和する睡眠が、逆に筋肉の緊張を引き起こす原因となります。枕の高さや硬さは重要です。
緊張型頭痛の治療法について
緊張型頭痛の治療は、まずは筋肉の緊張を和らげることです。姿勢の見直しとストレッチが大切です。無理な姿勢で長時間作業をしていないか、途中で休憩をとれているかなど見直しましょう。休憩中は、首や肩のストレッチを行い、筋肉の緊張をほぐしましょう。
マッサージも筋肉のコリを改善し、緊張型頭痛を緩和します。首や肩の筋肉を自分で軽くマッサージするだけでも効果的ですが、コリが強い時は専門のマッサージ師に依頼することも考えましょう。ただし、きつくマッサージしすぎると逆効果のこともありますので、緊張型頭痛のことを伝え、やさしく行ってもらいましょう。
筋肉の血流を改善させるために、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かることもいいでしょう。冷えは筋肉の緊張を強めますので、冬は暖かくし、夏場も冷房による冷えを予防しましょう。
薬物療法としては鎮痛剤と筋弛緩薬の使用がメインとなります。鎮痛剤は市販の鎮痛剤でも効果が期待できます。病院ではアセトアミノフェン、ロキソプロフェンやイブプロフェンなどがよく処方されます。筋弛緩薬は名前の通り、こった筋肉を柔らかくし、筋肉の緊張を和らげる薬です。
緊張型頭痛を持っている方は、ストレスを抱え込んでいる場合もあるので、そのような時は、抗不安薬を用いることもあります。
緊張型頭痛を予防するための生活
緊張型頭痛は、首や肩の筋肉の緊張が原因で起こりますので、筋肉が緊張しない生活が予防に繋がります。
筋肉の緊張は、長時間同じ姿勢でいることや、無理な姿勢が原因ですので、まずは姿勢を見直しましょう。前屈みの姿勢である猫背は頭痛を引き起こします。仕事で長時間デスクワークをしなければならない方は、1時間に1回は休憩をいれ、ストレッチをしたり、歩いたりしましょう。
日々の筋肉の緊張を翌日に持ち越さないように、夜はぬるめのお湯にゆっくり浸かって、血行を改善しましょう。湯船に浸かれない場合は、温タオルで首を温めたり、温シップを貼るのも効果的でしょう。
筋肉を休憩させるはずの睡眠も、合わない枕を使うと、筋肉を緊張させてしまいます。高すぎず、やわらかすぎない枕が予防に繋がります。頚部や後頭部は個人個人、形が異なるため、数個の枕を試したり、タオルで高さの微調整をするのもおすすめです。
緊張型頭痛との向き合い方
頭痛にはいろいろな種類があり、それぞれ治療方法が異なります。
頭痛で大半を占める緊張型頭痛と片頭痛では、対処法が反対となることもあります。緊張型頭痛は温めると改善しますが、逆に片頭痛は悪化します。
ご自身で診断をせずに病院を受診し、正しい診断を受けましょう。
引用
一般社団法人日本頭痛学会 https://www.jhsnet.net/index.html
慢性頭痛の診療ガイドライン2013 医学書院